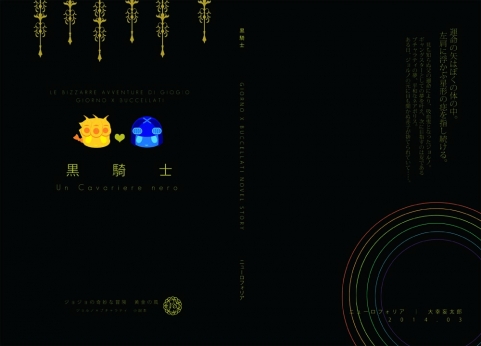2014/03/23 GBW3 発行の
ジョルノ×ブチャラティの三部作の最期のお話でした。【
当時のサンプル】
おかげさまで、完売いたしまして、再版することもないだろうということで、
全文を上げさせていただこうと思いました!!
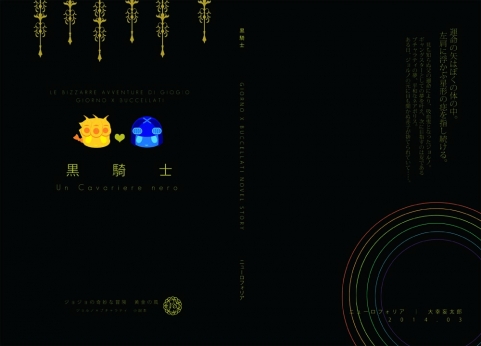

みささんがつくってくれた表紙と、すんばらしい挿絵!!
では、どうぞご覧ください!!
彼は欲望をコントロールできる人間でなくてはならない
権力欲や名誉欲 金欲・色欲のない人間で
彼は人の法よりも 神の法を尊ぶ 人間でなくてはならない
いつか そのような者にこのDIOが出会えるだろうか?
――ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーン・オーシャン文庫版 194P
第一章 星の子
2001/03/×× パッショーネ執務室
彼は『運命』を愛し、『運命』に連れて行かれた。
いつしかぼくは、そう考えるようになった。
絶対に敵うことのないライバルだ。
しかし、あきらめの気持ちでこう考えるんじゃない。
彼を連れ去った『運命』というやつの顔を真正面から見据えて、
一矢報いてやろう。そう決めたからだった。
「ポルナレフさんはぼくの父を知っているんですよね?」
机の上に一冊の本を置き、革張りの事務イスにもたれ掛かる。書類の山をのろのろとくぐり抜けて、机の上を一匹の亀がやってきた。その体には似合わぬ鋭い目をした顔をこちらに向けようと首を伸ばし、ぼくを見上げた。
「珍しいな、ジョルノが父親のことを聞きたがるなんて」
ぼくの手の下に置かれた本はオスカー・ワイルドの『ほしのこ』。身なりの貧しい両親を卑下したせいで、この「ほしのこ」は試練を受けることになる。
人間が一番最初に『運命』という何かに気づくのは、自分では両親を決して選べない、と気づいた時ではないだろうか。ぼくはその両親をずっと無視して生き続けてきた。
「いえ、もうそろそろ、ちゃんと知るべきかなと思いまして」
ようやく、組織もまとまって来たし、真正面からライバルを見据える時期が来たのだと感じた。ぼくより少し背の高いブチャラティの、空を見上げた横顔を思い出す季節になったから。
また春がやってきた。肌に新しい時代と共にやってきた春風を感じ、太陽の光を満面に受けた白い壁のぬくもりを感じた。街を歩けば、あふれる花々の香りが鼻をくすぐった。春はぼくたちに哀愁を連れてくる。
もう街の人々が笑顔を向けていた、あの大きな体はぼくの隣にはない。少しだけさみしくなって手を握りたいなと思っても、ぼくの隣には、手をつなげる相手はもういない。
彼が残してくれたのは、ネアポリスから麻薬を失くし、街の人々が幸せに暮らせる街にするという願いと、童話と言う宝物。疲れた時にふっと手を伸ばすと、その単純な願いと、わずか数ページの物語はやわらかい響きで脳に染み渡り、彼との思い出をやさしく揺すぶった。その単純な構造に安心する。そこにはいつも奇跡があった。
たまに、ぼくを叱りつけるような童話もあったけれど、それすらも宝物だ。その童話はぼくに安全に、間接的に失敗を経験させてくれるから。
亀は困ったように一度視線をはずし、そしてもう一度つぶらな目を見開いてぼくを見た。
「どちらの、父親をだね?」
きっと亀と話すぼくは、童話の人物のようだろう。
「あなたの、よく知る方の父を……」
ポルナレフさんは遠くを見つめて、ふぅ……とため息をつく。
「Dioかね」
「あるいはディオ・ブランドー」
腕を組み替えて机にうつぶせる。亀と視線を合わせて、まるで寝物語をねだる子どものようにまばたきをした。
亀はゆったりと語りだす。その歩く人間の頭蓋骨そのままの姿で。はるか過去Dioと名乗った王は己の力に絶対の自信を持ち、誰も信頼しなかった、と。そのやり口は卑怯で残忍、しかし彼は闇の中一人、堂々たる悪の王であったと。
語り終えた亀は、しばらくぼくの方を見ていたが、やがて首を振った。
「過去は情報でしかない。これが全てだと思わんことだ。彼が崇められていたのは事実だが、オレはDioの非道も見てきた。被害にあった。だから決してフェアな語りは出来ないだろう。息子のおまえが望むものを与えられたかどうか……。それに、今は目の前にある戦いが重要だ……過去に縛られるのはいい事とは言えないな」
「……そうですね、ありがとうございます。単なる興味にすぎません……仕事には影響がないようにします」
父がどんな人物だったか、そんなことにはあまり興味がなかった。父はもう死んでいたからだ。トリッシュ、彼女がぼくの目の前で経験した血の繋がりによる『運命の連鎖』。ぼくにはそれは当てはまらないと思っていた。もう父は死んでいる。ぼくには何の影響も及ぼさない……そう思って無視して生きてきた。
「そういえば承太郎がこんなことを言っていた。DIOは天国を目指していたと……」
しかし二年前、母と同じ黒髪だったはずなのに、あやしい神父からもらった父だという写真の男と同じ金髪に突然染まり、以前から当然起こるものだと思っていた、生命を生み出す奇跡は形を持ってぼくの前に姿を現した。彼はぼくにゴールド・エクスペリエンスと名乗った。ポルナレフさんによればそれはすべて『父の血』によるものだと知らされた。ぼくの二人の父はどちらも話題にさえ出なければ一生知ることが無かった父だ。しかし、運命はぼくの無知を許してはくれなかった。
そして今、ぼくはさらに『父の血』に振り回されて今、ゴールド・エクスペリエンスと別れを告げて、吸血鬼となった。
昼間に寝て夜に起き、血流のようにネアポリスの暗部を巡るパッショーネを動かした。
太陽の祝福を父は与えてくれた。そして太陽の祝福を父は奪った……。
だが、どちらの乳を恨む気持ちもないし、これから先、意識することもないだろう。ただ偶然、皮肉にも、昔Dioと名乗る父がそうしたように、夜の闇に過ごし、肉の芽ではなく恐怖で人間を縛り、動かしている。
「ポルナレフさん、ぼくは父に似ていますか」
亀の目がギロリと光ったように見えたのは……一瞬だった。
「私は……おまえを信じているよ」
彼はぼくの監視役だ。もしぼくが正義に反することを始めたら、すぐに始末しようとするだろう。ただ、ぼくはブチャラティの言葉をきちんと守りたいと思っている。ネアポリスを麻薬の無い平和な街にすること、この目標がなくなったとき、ぼくは父の血にほんろうされて『正義の心』を亡くすのだろうか。
「ギャングスターになるというのは想像以上の淀みを受けるものなんですね」
机においた写真を傾ける。護衛チーム全員でとった唯一の写真。ブチャラティは何に気を取られたのか、少しとぼけた表情に写っている。この写真はなんとも彼らしくて、見ているだけで笑みが浮かぶ。
「ブチャラティとの出会いがないまま、ギャングスターになっていたらと思うと……少しおそろしいです……」
亀の表情が少し笑った……ように見えた。
「ああ、だからおまえを信じられるんだ」
人を疑い、肉の芽を使い、思うがままに人を操る父は暗闇の中、ただ一人だたに違いない。彼には『友』はいなかったはずだ。
母や、腹の中にいたぼくを実験体としか見なかった彼には、誰かをこんなにも愛する気持ちがわかるまい。
「おまえが誠実に人を思いやれる人間だから信頼できる。誇りに思える良い友を持ったな」
「……ええ……」
思わず視界が霞んだ。
「ジョルノ、おまえは間違いなくジョースターの血統だ。今でもそう感じている。無用な心配はするな」
「……グラッツェ……」
二人の父の血が、ぼくの中には流れているという。
吸血鬼であり暴君であったDio、ディオ・ブランドー。
あと一人はジョースター家の血筋、ポルナレフさんもその源流を知らないというが、その血筋の人間が持つという黄金の魂をぼくに感じると、そう言ってくれた。
ぼくは、あの一週間と少しの大激変で全ての運命を乗り越え、生きる意味であった、ギャングスターになるという夢を叶えた。全ては彼と彼の仲間たちが支えてくれたから。だからこれからはブチャラティ、彼の夢を叶えるために生きていく。
太陽の光に当たると、肌が火傷したように赤くはれて水膨れができ、鋭い痛みを残す。しかし、じっとしていれば一日とたたずにその傷は跡も残さずに治った。
食事はあまりとらない。死んだ食材を口に運ぶとこちらまで疲れてしまうからだ。しかし、腹持ちはいい方で、そうしょっちゅう食事をしなくても大丈夫なようにできている。
身体能力も普通の人間の倍になり、夜になれば、唯一の恐怖の対象である太陽も消えて、何一つ怖れるものもない。歩いての行動範囲もずいぶんと広がった。一晩であればネアポリスの端から端まで行けるかもしれない。しかし睡眠は必要なようで、律儀にも昼の時間になれば自然と眠気がおそってきた。
ポルナレフさんはぼくが眠っている間、ミスタを通して指示を出していた。全てを任せて安心して眠る。星形の痣のある左肩に触れるようにして……目の前には、もう一人の父、ディオ・ブランドーの写真を入れた定期入れを置いて。
ぼくは、どちらの父の『運命』を引き受けるのだろう。
『運命』を真っ直ぐに見つめたあなたなら、それも見えていたのだろうか。もっとぼくが父に興味を持っていて、あなたがもう少し長い間ぼくのそばにいてくれて……ぼくの……星をいっしょに眺めてくれたなら……それも、今頃はわかっていたのだろうか……。
今さらながらこうして、後回しにしていた『運命』に振り回されている。ぼくはあまり後悔しない人間だと思っていたが、彼を失ってからは、過去を振り返って後悔するようになった。
2002/04/06 隠れ家のホテルにて
一時的に隠れ家として使わせてもらっているホテルの一室。誰も近寄らぬ極上のスウィートルーム。ありあまる金で買い集めた書籍を山のように積み、ひたすら目を通していた。窓の雨戸まで閉じたこの部屋では時間の経過を知らせてくれるのは時計だけだった。廊下の足音は昼も夜も耐えないし、報告だって待ってはくれない。。
マフィアのように血の掟で縛られているわけではないけれど、ある一定の暗黙はさすがにある。パッショーネは基本的に自由だと言っていい。そんな組織の力の源はその自由さだ。幹部といっても信頼を金に変えて証明すれば幹部にもなれるし、力を使った下克上も可能といういかにもギャングらしいところにあるのかもしれない。
だからこそ僕のような若造が姿を隠して、こそこそ隠れてボスをやっていられる。トップに立てば、パッショーネの自由さこそが力であり、同時にもろさだということがよくわかる。力、金、人脈、どれか一つでも欠ければ、ぼくも簡単に引きずり降ろされていたかもしれない。
「ボンジョールノ!ジョールノ!」
真昼時だというのに雨戸も閉め切り、ぼんやりとした、だいだい色の電球だけが点った部屋に、底抜けに陽気な声が室内に響きわたった。閉じた窓のすきまからやってくる太陽のこぼれ日を前に、少しまどろみ始めたところだったが、久しぶりにやってきた友を迎え入れるため、ブランケットをゆっくりとまくった。膝の上のの本がゴトリと音を立てて、足がかるく埋もれるくらいやわらかな絨毯の上に落ちた。
「うぉ!まぁたおまえ、こんな暗い部屋で、そんなゴッツイ本読んでたのかよ……おめめが悪くなっちまうぜー?」
ミスタは手を振って、目の周りをうろちょろするハエを追い払うような仕草をする。今はもう、声も聞こえないし、姿も見えないが、あのかわいらしい小人たち、セックス・ピストルズがキンキン声でぼくをからかっているのだろう。
「ん?もしかして、今ジョルノが落としたそれが最新の密輸武器だったりして?これなら警察の目も欺ける?……その上、殴るだけで人を殺せそうなこの重厚さだもんなぁ!」
ミスタは大げさに驚いてみせる。この本は五百ページほどしかない。さほど厚い本とも思えないのだが。……それはともかく、大切な本を取り落としてしまい、あわてて拾い上げた。背表紙を確認したが、ページの折れもない。安心して溜め息をついた。。
「中身はミスタでもわかるよ。アンデルセンの童話集だし」
「そうか、それじゃあ今度、貸してもらってもいいかな?」
遠慮のない友人は、ドアを開けてそのままズカズカと、ぼくの部屋へ入り、確かめるためにぼくが差し出した本のページをめくる。ブチャラティがくれたやつか?と質問をするので、ぼくがうなずくと、ほほえみをうかべた。しかし、そのたくましい体の圧迫感が息苦しい。少し離れてくれよ、と眉をひそめて見上げる。そんなぼくの気持ちも知らずに、ぼくの巻き毛をワシっと掴んで一言。
「あいかわらず、健康に悪そうな生活をしてるんだな」
「……ぼくを子ども扱いしていい人間はただ一人です。放してください」
「はいはい……オレだって一応、三つ年上なんですけどねー?」
頭部を包み込む青い帽子の上からボイボリと頭をかいたのは、戦友のグイード・ミスタ。
「三つしか違わない」
眠い頭でその手をうっとうしく払う。
「ブチャラティだって五つ違うだけだろう」
「五つ違えば十分違う。というか、ミスタとブチャラティじゃ精神年齢が全然違います。あと、不意打ちは禁止です……その名前は不用意に呼ばないで」
思わず鼻をグスッと鳴らした。それを聞いたミスタは、おまえの唯一の弱点だからな、とうれしそうに言う。
「おーお、こわいこわい。バンビーノは一年経ったくらいじゃ治らない?」
ハハハ、と乾いた笑いをもらすミスタをにらみつけた。意識するとまだ、感情が揺さぶられるのは、あなただって同じじゃないか。それくらい、ぼくらにとって、彼の存在は大きかった。
「メシ、ちゃんと食ってんのか?こんな顔見せたら、おまえのマンマのブチャラティがカンカンに怒るぞ」
頭に指で角を生やし、口元はおどけているが目は真剣だった。僕のメシに対する質問は最高のブラックジョークだ。しかし彼はぼくを大切な人間だと思っていてくれるからこそ、尋ねずにはいれないのだ。
「……ちゃんと食べているよ」
いつの間にか口の中が乾いている。せっかくの来客だし、あとで女中にカッフェでも持ってこさせよう。
「そうだね、今年に入って三人ほどいただいたよ」
人を恐怖で支配するには丁度いい体質なのかもしれない。一番おおっぴらに反逆を起こしている人間を調べ、彼が一番油断しているときにやってきて、ペロリといただく。その後、カラッカラに干からびた食事の残りカスにほんの少し、人がやったことであるという証拠、パッショーネの紋章を入れた名刺を差し入れておくだけだ。あとはそれを見た悪人だけが恐怖してくれる。
最近はその死に方があんまりに不自然で、幽霊の仕業だと騒ぎ立てる人間が出ているらしい。その噂は少し変化して、見るだけで恐怖に縮みあがる謎の黒騎士という幽霊の噂話が流れはじめているらしい。幽霊と言えば幽霊か。真っ暗な部屋から出ないひきこもりなだけなのだが。
その幽霊はものすごい超能力を持っているというのに、ボスに忠誠を誓っていると噂は伝える。それは裏返せば、ボスの力の絶対性の証明でもあった。パッショーネはギャングだからこそ、恐怖での支配は特に効く。つまり、この噂は勝手に流れ始めた都合のいい噂、というわけだ。
ポルナレフさんは噂を放置しての恐怖支配には、いい顔をしてくれないが。ぼくが食事をするカモフラージュになっているのだし、一石二鳥だと説明すれば、しぶしぶ許容してくれた。
「オレに裏切り者を始末させずに、テメーが現場に向かってその場で頭からパックリ食っちゃっても、全然かまわないんだぜ?」
シシシっとミスタは笑う。
「そんなにたくさんの人間を食べたら、ぼくのおなかが破裂しちゃいますよ」
パッショーネを襲うのは、なにも内部の人間だけじゃない。外部の組織だってぼくたちの縄張りを狙っている。ぼくが食べても大丈夫な人間は山のようにいるが、それだけ大勢が一気に姿を消しては、他の問題が起こってしまう。それに、ミスタという腕のいい暗殺者がいることで、パッショーネの力をさらに誇示できるのだから。
だけど、ぼくにとって、食事は恐怖だった。組織の秩序のために殺すとはいえ、罪人の血を体に流し込むのはなんだか気分が悪い。そういう人間たちに生かされている自分がなんだか、もどかしい。
ブチャラティなら言ってくれたろうか。ぼくが食事をするのを怖がらないように諭してくれたろうか、それとも、そんな僕を否定しただろうか。
「変なところブチャラティに似やがって……」
立ち上がろうとした僕のクセ毛をまた、大きな手で頭ごとつかむように、ワシワシと撫でられる。
「すーぐ表情も変えずに、真顔で考え込むとこ、とかな……」
似ているなんて言われては、なんだか悪い気がしなくて……。肩が少し寒くなってきたので、かけていたローブを体の前でギュッと握りしめた。
「お互い、あの人を亡くしてから鈍くなったよな」
どれだけあの人が心の支えになっていたのか、4月6日、今日と同じ日付に彼は亡くなった。ボスを倒した後、当然生きている、と思っていたブチャラティが目を見開いて横たわり、ぐったりとした様を見たミスタとトリッシュは、呆然とコロッセオに立ち尽くした。
二人は驚きもしないぼくを不思議に思ったようだが、拳をきつく握りしめ、血を流している様を見て何も言えなかったと教えてくれた。
ーー悔しかった。まだ彼の死を先延ばす方法はある、そう思っていたから。
いくら生命エネルギーを注ぎ込もうとしても、その体はもう生命のない物体としか判断されず、無数の花を咲かせ、さらに注ぎ込まれたエネルギーで枯れ果てていった。ミスタもトリッシュも、そんなぼくの姿を見て、嫌でもブチャラティの死を知った。
彼の性格のように几帳面に柄が織り込まれた白スーツ。銃で撃ち抜かれた穴からは乾いた血がポロポロとこぼれ落ち、体温も消えて冷たくなった物体。それだけがコロッセオに落ちていた。
あの日から、生き残ったぼくたちは、感情に対してひどく鈍くなった。
ミスタにとっても、トリッシュにとっても、ぼくにとっても、彼は最後に帰る場所だったから。
「いろいろあったけどさ、誰が悪いってわけでもないし……全て片づいたんだ。今はおまえがボスだしさ、トリッシュだって故郷でうまくやってる……オレだって仕事さえもらえればメシにありつけるし……問題ない……」
ミスタはひとりごちる。ぼくには話そうとしないが、彼なりの後悔があるようだった。あの時、魂が違う人間だったとはいえ、ブチャラティに弾丸を撃ち込んだのは彼だったから。
「気にする必要はないんですよミスタ。あなたなら見ればわかるはずだ……何が致命傷になったか」
彼の遺体はキレイなものだった。魂という物があるとして、それがすっぽりと抜け落ちた……といった様相だった。外傷も無く、死因が特定できない状態だったのが、逆に皆の後悔を増幅させていた。
ミスタの口元にまた笑みが戻る。でも悲しそうな表情は変わらない。
「後悔なんてするだけ無駄です。無駄無駄……」
そう言って、まだへこむミスタを鼻で笑ってやる。ミスタは、そんなぼくの頭にゲンコツを落とした。
「可愛げがないなぁ、おまえは本当に!一番後悔してるのは誰だっていうんだよぉ!」
落とされたゲンコツが、そのままグリグリと襲ってくる。
「いたたたたた……や、やめてください!」
「辛気くさい顔して無駄とか言うな!説得力ねーんだよ!」
「わ、わかってます……ぼくが……誰よりも後悔してるって……」
彼との思い出をすべて清算するのに一年では足りない。一週間とちょっとの出会いのぼくでもこれほど苦しいのに、何年もつきあってきたミスタの苦悩はどれほどのものだろう。
えぐるようにやってくる心の痛みが、どんどんぼくたちの感情を鈍くさせていた。過去という錆が、ぼくたちの心を浸食していた。それを振り払うために、忙しく動き回っているというのに、こうやって少し立ち止まるだけでボロが出る……。
四方を本の山にかこまれたこの部屋に、コンコンと軽いノックの音が響きわたるまで沈黙が続いた。ゆっくりとドアが開き、か細い女性の手がのぞいた。左手首をぐるりと囲むように少しだけ薄い傷跡が残っている。
「ジョルノ、いいかしら?バカが邪魔してるみたいだけど、大丈夫?」
もう片方の腕には、布にくるんだ小さな赤子を抱えていた。腰まで入ったスリットからのぞく細い足をゆっくりと動かして、ヒールを絨毯に沈めながらやってきた。ビビッドなピンク色、大きくウェーブさせた前髪がはずむ。
トリッシュが人差し指で赤子をあやすが、赤子は不満そうにアッアッと今にも泣きそうな声を上げた。
「どうしたんだい?その子、ミスタとトリッシュの子なのか?」
ふふっと笑いながらトリッシュに近づいた。トリッシュは顔を真っ赤にして今にも湯気を吹き出しそうだ。
「バババババ、バカなこと言わないでくれる!?」
「そ、そうだそうだ!バカなこと言わないでくれるぅ!?」
ミスタが地団太を踏むようにしてトリッシュの口調をまねする。トリッシュは真っ赤になってうつむき、膝を弾ませて赤子を揺らした。
「まったく、しょうがないな、頼りないパーパとマンマで困るだろう?」
ほほえみながら赤子の顔をのぞき込む。まだ目も開かぬ赤ら顔。まだ薄い黒髪に指を滑らせて頭皮を撫でる。赤子はまたアッアッと声を上げると、マカロニくらい小さな指で、自分に触れた手をとらえようとむずがった。
「この子は……神の落とし子よ……」
トリッシュは言葉を選んでそういった。
「きっと洗礼さえも受けてない」
神から愛を受けないと言うことは、誰からも愛されない不幸な命ということ。僕は不憫に思いながら、その小さな手に人差し指をつかませた。力も弱く、少し指を動かしただけで離れてしまいそう。
今は生命を奪って生きる生物になってしまったが、今でも相手の生命力を、その血流で感じ取ることができた。
それゆえに感じる赤子の生命力は微弱だ。母親から初乳はもらえたようだが……そこから先はどこかに放置されていたのだろう。まるで自分のようだ……いや、ぼくよりもひどい環境に置かれている……。ぼくはまだ、せめて、生まれて少しの間は親にかまわれていたのだから。
この子をどうにかしてあげたいと思ったが、今のぼくにはどう対処していいかわからない。せめて、ゴールド・エクスペリエンスがいれば……。
「ねぇ、今日が何の日か知ってるでしょ?」
トリッシュは言う。今日は4月6日。ちょうど一年前に全ての決着が付いた日。ギャングスターになるという大きな夢が確実になった日。そして……神に誠実すぎるゆえに人間離れしていた彼、ぼく達の愛したブチャラティが亡くなった日。
「だから私たち、ここに来たんだけど……この宿の親父さんがこの赤子を抱えて困っててね……どうしたの?って聞いたら、捨て子だって……」
おなかが空いているのだろう。握りしめた僕の指をちゅうちゅうと吸った。
「こら、だめだ……ぼくの手にはほこりがついていて汚いよ……」
指をとりあげようとしても、あまりの力なさに折れてしまいそうで、ためらってしまう。このまま死ぬ、それがこの子の『運命』なのか?
「ホテルのオーナーがな、噂で、パッショーネのボスがここに宿泊している、と聞いたらしい。それが本当なら、この子を引き取れとは言わないから、せめて名付け親になってほしいって言うのさ」
最近よくうろつくようになったガラの悪い人間を不審に思い、観察し、耳をそばだてているうちに、どうやらここにボスがいるらしいと、宿屋のオーナーは予想したらしい。オーナーはきっと、この子のために、まだ話しやすそうなミスタとトリッシュにすがるようにカマをかけたのだろう。
「おまえがゴッドファーザーになれ」
ぼくと赤子を見ていたミスタが唐突に言う。
思わず驚いて一歩後ずさった。でも赤子は指を放さない。それを見てトリッシュがうれしそうに笑った。
「それがいいわ!ギャングスターの加護があるなら、この街にいる限り、安全に暮らせるわね!」
そう言って、思わず顔を上げたぼくと視線が合うと、トリッシュはキュートなウィンクをして見せた……。どうやらこれは、最初から仕組まれていたことのようだ。仕方がないなと笑う。
「もちろん、断ったってかまわない。無茶な話だもんなぁ?」
ミスタも、断るなんてないだろうけど?と笑いながらぼくを見る。
「でも、これって『運命』だって思わないか?」
あの青年はいつも『運命』を信じていて、そのためになら生きも死にもしようと考えていた。ゆえに行動が突飛だったり、驚くほど簡単に命を捨てるような行動に出ることがあった。だけどそれはギャングという命を懸けた職業には非常に向いている性格だった。
そんな彼の命日、偶然、仮住まいにしているホテルに捨てられた赤子。これが『運命』でなくてなんというのだろう?
「……引き受けてもいい……その後は孤児院で生活することになるだろうけどね……」
「ああ、それでいい。その孤児院にはしっかりいい護衛をつけてやってくれよな」
ミスタは歯をむき出してニッと笑う。
トリッシュはうれしそうに頬を染めて、黒髪の子を揺らした。
きっと三人ともバカなことを考えているんだ。もしもこの子に、彼の名前を付ければ、それが『運命』なのだとうなずいて、彼がぼくたちの元へ戻ってきてくれるんじゃないか……と。
照れくさいような空気が三人の間に流れた。三十を前にした大人たちが夢想するにはあんまりに子どもじみていたけれど、ずいぶんと久しぶりに、心の中に『希望』を感じていた。
◇ ◆ ◇
ぼくの姿が見えないように信頼できるメンバーが壁にして、ぼくと赤子と神父を取り囲ませた。こんな場所に人殺しが集まるなんて罰が当たりかもしれないが、それもこれもホテルのオーナーが全部引き受けると言ってくれた。果たして神が肩代わりを許してくれるなんて思えないけれど、なんとなく心強く思った。
神父はまだ子どものぼくを見て驚いていたが、ぼくがパッショーネのボスだと伝えると、うやうやしくお辞儀をした。
この孤児院にはある程度寄付をしているし、おおっぴらには言えないが、この神父はぼくらのような人間もこのネアポリスには必要だと信じている、少し変わった神父なのだ。
神父は聖水に指を浸し、洗礼名を授かった孤児の額に触れた。
「この子の名前は、ブローノと名付けてくれ」
孤児院から去り際、組織の代役だと名乗り、ミスタとトリッシュに見守られながら、孤児院のシスターにブローノを預けた。とても静かに眠る赤子を抱いて、シスターはきれいな黒髪ねとほほえむ。
「ぼくらにとって目の前で奇跡を起こした聖人の名前なんだ……同じような黒髪をしていた……だから、ブローノと」
「まぁ、とても素敵なお名前をいただいたのね……」
ぼくたちがギャングだと知っていても、神の加護のもとに奇跡を起こした人間に貴賎はないと言って、シスターはほほえみ、ギャングの僕たちに頭を下げた。
洗礼を受けない子どもは神に愛されることはない。肉の父母から捨てられた彼は、せめて神に愛されてほしい。
そして、本当の父母がわからなかったとしても、不名誉かもしれないが、必ずこの街のどこかで見守っている……父親を思いだしてほしい。
シスターはぼくに名前をきいたが、ただ首を横に振った。
「ぼくはあくまで、ボスの代役ですから……」
2001/04/×× 彼との一夜
「不思議な痣だ……」
熱を放ち、湿った肌。よく締まった肉体は僕の腕に抱きしめられながらも、そっとぼくの肩を抱く。蒸れた事後の香りが、疲れた脳をしびれさせる。視界は涙にゆがみ、端に彼の黒髪を写すのみ。
油断しているところに、スリっと指で左肩をこすられて、ビクンっと思わず体を反応させた。
「んあっ……ブチャラティ……何を……突然っ……」
肌がへこむほど強く、でも動きはゆっくりとやさしい。その位置はあの痣のある場所。きっと物珍しくて形をなぞっているのだろう。
「星の形をしている……」
あの深い海のような色をした瞳に星の形を映して興味津々でのぞいているのだろう。肩にぽってりと厚いくちびるが当たり、話すたびにあたたかい吐息がかかる。
「これは……生まれた時からあるのか?とてもクッキリ浮かんでいる……」
ようやく全てを出し切って萎えはじめた僕の肉棒が、彼の腹にこすれてまた、うごめき出す。
「やめてください……ブチャラティ……」
また元気になってしまっても、きっとブチャラティは二度目はさせてくれないだろう。ヤリすぎは猿になるぞと叱るのだ。そのくせ、からかうから困るのだ。それがわかっているからスネていると、フッフッフ……と顔を伏せてブチャラティは笑う。
「くすぐったいのか?」
きっと、星の形の痣をいじっていることに対して聞いているのだ。
こういう変なときに鈍感な彼が憎く思う。
「……気持ち……いいです……」
少し腹立ちを声に込めて言い、ぼくの上に乗る少し大きな体を下に敷く。
「っあ!も……もう少し……見せてくれよ……」
ブチャラティが上機嫌に笑う。筋肉質ながらもやわらかくてあたたかなその胸に顔を埋めるようにして抱きしめた。これなら無意識のおいたもできまい。
「ジョルノはこれを見たことがあるのか?すごく、きれいだぞ?」
まだしばらくジッと星形の痣をながめていたが、少し首が疲れたのだろう、頭をようやく枕に沈める。まだ二人とも鼓動が収まらなかった。
「見えると思いますか……?鏡二枚を使ってやっとですよ?」
ようやく見えた海のように深いブルーの瞳は潤んでこちらをじっと見つめている。
「それはもったいない」
ブチャラティの笑む口元にドキンっと心臓が飛び跳ねた。少しずつ収まっていく彼の鼓動になんだか腹が立つ。肩に腕を回されて力強く抱きしめられる。身体全体を包み込む彼の体温がとても気持ちよくて、ついつい怒りも静められてしまう。
「この痣は、幼い頃からあったらしいんですが、今ではもうこれを見た人間とは会うこともないですし……いつからあったか、確証はありません」
愛のある母親が育ててくれたならば、その痣を教えてくれたかもしれない。それに父親ですら、ぼくに暴力は振るっても愛情のかけらすら与えてはくれなかった。こんな風にこの痣を愛おしく思ってくれた人間は、彼以外いない。
「これは、神の奇跡だ」
彼のロマンティックな言葉がくすぐったくて、今度はこれ以上痣が見られないように、よじのぼるようにして彼の首筋に顔を埋める。いい香りがする。ブチャラティの髪の香り。だけどそんなブチャラティのロマンティックな言葉にはうんざりしている。
彼はいつも浮ついた事を言う。もっと現実を見ればいい。そうしなければきっと、闇の中の真実を見つける前に、数千年使っても存在を実証されることのない、彼の愛する神や運命を選んで、殺されてしまうと思ったから。
「神や運命……ブチャラティはロマンチストすぎる……」
そのためには命を捨てられるほど彼は神や運命を愛している。ぼくを愛しているのも運命なのか?とたずねればきっと、迷いなくうなずくかもしれない。そうだ。神が与えてくれた運命なのだから、と。だから、こわくてそういう質問は、まだしていない。
「そういうおまえは少し、ひねくれすぎている」
地震が起こったみたいに揺れる。ブチャラティが笑っている。振動がくすぐったくて、ぼくも笑うしかない。
「……笑ったな?じゃあこれはどうだ」
ようやく笑いが収まってから、ブチャラティは言う。
「この地球が生まれた時から働いているものは何か知っているか?それは『重力』だ……地球が月を引っ張るように、人と人が引かれあう……なぜなら、『重力』は地球に生まれながらにある法だからだ。これを人は『運命』と呼ぶ。これなら理にかなっている。ジョルノ、おまえの好きそうな話だ」
よくもまぁ、と思いながら笑う。
「いいえ、十分ロマンチストです」
どうせ僕の星形の痣にかけて思いついた話だろう。またブチャラティが笑う。揺れる視界に、少し困ったような表情が見えた。
「……でも、この話は本当なんだ……」
「……あなたと引き合わせてくれたというなら、ぼくはこの星形の痣に感謝しましょう……」
ブチャラティはほほを染め、満足そうにほほえんだ。
「ジョルノと出会ったことが『運命』で……オレを……心に広がりゆく淀みから助けてくれたのも、ジョルノなんだ……」
太陽と月か……朝の海か、夜の海か……光輝く太陽の錘か、夜をほどいた闇色の糸か……。生命の厳しさに突き当たったからこそあこがれる人間か、生命のやさしさに染められたからこそ、やさしくあれる人間か。あなたとぼくは、驚くほど正反対なのかもしれない。
「……何を考えているんだ?」
「……あなたに影響されすぎた……笑えるほどセンチメンタルなことです……」
ぼくはブチャラティの体から降りて、サイドテーブルから本を持ち上げた。
「マンマ。本を読んでください」
とっておきの笑顔。ブチャラティの顔が真っ赤に染まり、不機嫌の色がうかがえた。
「……おまえなぁ……」
あなたの思想に染められるのは楽しい。でも、ぼくもいつか、あなたにぼくの思想に染まってもらいたい。いつかはちょうど半々、とけ込みあって同じ色になれるだろう。
2012/03/×× 夜のネアポリス
「うっが……あ……が……」
ぼくは男の体を強く抱きしめ、暴れる体の骨を折って固定する。死ななければ多少味が悪くなっても問題ない。
「ひぃ……許して……ゆるし……」
子どもたちに麻薬を売る奴らがいた。無抵抗な子どもを選び、無理矢理麻薬を注射して中毒症状を引き起こし、街に放つ。気の弱い彼らは街の人々に暴行をふるう事なんてできない。ただ救いを求めて祖父母や両親に暴行をし、目の前に転がった財布を手に麻薬を買いに走っていた。
「……あんたたちの血からは、麻薬の味がしないね」
首を傾げ、月光の下で恐怖にゆがむ顔を見た。
ぼくは久々に最悪の人間を前にしていた。
そうやって悪事を働かせ、誰も頼るものがいなくなった子ども達をギャングに育て上げ、ネアポリスで稼ぐことができなくなったと知ったとたんに……こいつらはほかの街に子ども達を売り払い始めた。
「知っているんだね、麻薬の恐ろしさを……だからあんたたちは子どもたちに麻薬を売っていたんだね……」
青白い月光はきっと僕の顔をより青白く浮かび上がらせるだろう。ぼくの癖の強い金の巻き毛は銀の糸に変わるだろう。
そして奴らは知らない。ぼくが彼らの頼るパッショーネのボスだということに。
「ぎゃがが……あが……」
ほほをつぶし、その顎を引き裂いてしゃべれないようにした。相手はただ赤く染まっていく月を見るだけだ。
ぼくの手は彼の額を突き、そこから生命エネルギーを吸収していく。額から流れ出た手は彼の視界を赤く染めていき、じわじわとやってくる恐怖を星空をながめて死んでいくのだ。
星は運命を教えてくれるとブチャラティは言った。
「死に際に見る星は……どんな色をしているんですか?どんな運命を語っている?」
ぼくの腕の中で彼は、まるでねじれて育った樹木のように枯れ果ててしまった。そこにパッショーネの紋章入りの名刺を刺しておいた。
「……これで、子ども達が助かればいいけど……」
麻薬はなかなか抜けるものではない。今は部下達がこいつに麻薬漬けにされた子ども達に、外部から麻薬を売っていたやつらを始末しにいっているはずだった。
「……ブチャラティ……ぼくは……間違ったことをしていますか……」
ぼくの体の中に流れる罪人の血。年々増していく食欲。
だいぶ組織内の構成が整ってきたとはいえ、まだまだ悪知恵を働かせる奴らが出てしまう程度にはザル……とも言える。
「あなたはやさしさで変えていくのに、ぼくは恐怖で変えていくことしかできない……」
でも、星空をながめるとまだ、彼の目がそこにはあるような気がして心が軽くなる。そして同時に『運命』の強さというものも強く感じるのだった。恐怖で支配したという父の目も、この空にあるのだと。
◇ ◆ ◇
ロマンチストのブチャラティが言った『引力』の話。くだらない会話かもしれないけれど、今でも鮮明にそれを覚えている。身体の一部一部に記憶を宿すことができる……は聞いた事があるが、これがそれなのだろうか。痣のある場所に指を触れると、あの時の記憶とともに、その引力の話を思い出す。
「ブチャラティは言ったな……きっとおまえの両親のどちらかにこれと同じ痣があったんじゃないかって……」
はじめてこの痣を美しいとほめられたから覚えているのかもしれない。小さいことだろうけど、とてもうれしかったから。それとも、数少ないブチャラティとの性交の記憶だからだろうか。どちらにしろひどく感傷的で幼稚だ。
「バレたら笑われるな……」
またバンビーノ扱いされてしまう、と気が引き締まった。だからこそ、ぼくは空をながめる。彼が生きていた頃のぼくなら考えもつかないほどロマンチストになってしまったということだ。ぼくも今年で二十六、今では彼よりも年をとってしまった。
なんでセックスなんてしてしまったのだろう、ただ、あの時はひたすらにブチャラティに抱きしめられたくて仕方がなかったのだ。彼ならば、絶対にぼくを抱きしめてくれると知っていたからだ。
その胸板に額をつけてもいやがらず、その鼓動を聞いてもいやがらない。そして、ぼくを叱るように彼の口から言葉が一つ一つ飛び出すたびに、身体を揺らすその声の響きが、ぼくの中の甘い部分を揺さぶるのだ。
それは尊敬であり、愛情だ。そして彼の肌の温もりに、呼吸のうわずりに、わずかの劣情も混じりだす。いたずら心でズボンの上からその性器にふれ、いつも大人ぶっている彼の声の上ずりを楽しみ、誘うように開いたスーツの胸部分に手を差し入れて、なめらかなレースでできた下着の上からその胸板に触れた。ぼくの指がつと胸の突起に引っかかると、聞いたこともないような甘い声が漏れる。
その時に知るのだ。ぼくが彼をどうしたいかを。彼をどうしようもなく、体の奥底、心の奥底まで支配したいという欲求が湧き上がる。
その時だけ……ブチャラティはバンビーノ扱いはしなくなる。二人が同じ立場でいれる、数少ない時間だった。それが愛からくる欲求だと教えてくれたのはブチャラティだった。そうでなければ、こんなことはしてはいけないと叱るのだ。
普段は見せない痴態を見ることが許されたのもぼくだけだ……そう思うともっともっと、ブチャラティを愛おしく思った。彼の一生の中で、一番彼を愛し、求めたのはぼくだと、そう断言したいくらいに。
ホテル最上階の窓から、暗闇に包まれてもなお、生活の明かりを灯す街並みをぼんやりと見下ろす。僕の手に握られたタブロイド紙はクシャリと音を立てた。
大きな見出しにはこうある。『ブローノ・ブチャラティは本当に正義の使者なのか』
孤児院や病院に定期的に届けられる多額の寄付。その差出人はブローノ・ブチャラティと書かれていた。その名を探るといくつか候補が現れるが、どれも平凡な人物ばかり。しかし、その中に一人だけパッショーネの幹部が混じっていた……。とある。
ボス死亡の噂が立つと下克上をねらってあらゆる人間が動き出し、そのいざこざに巻き込まれた街の人々はパッショーネにいらだちを感じていた。でもそれもたった一年だけ。すぐにまたパッショーネは街を流れる機能の一つとしての力を取り戻した。ぼくたちの努力により街にパッショーネは必要だと認められたのだ。
パッショーネのボスは『見えないボス』。彼はまるで干からびた樹木のようになった死体を残す凄腕の暗殺者を使っている……という噂があった。その殺害はいつも闇夜に紛れて行われると思われていた。夜中元気にしているところを目撃された被害者の失踪は、いつもその朝方に確定されたからだ。
暗殺者はボスへの忠誠のすごさに黒騎士と仮に名付けられ、恐れられまるで童話の登場人物のように存在がぼやけているのに、新しい『見えないボス』は黒騎士の暗躍のおかげで信じるに充分な証拠となった。
荒れ果てた組織をあっという間に平定した『見えないボス』と『黒騎士』という闇のヒーローと同時期に現れたのが、孤児院や病院に多額の寄付をよこす『ブローノ・ブチャラティ』というヒーローだった。
「……もう粛正は充分行ったはずだ……」
僕の身体に流れる罪人の血は三十を数えていた。反乱をたくらむ組織の人間や、闇のヒーローと街のヒーローを暴いて街に混乱を起こそうという記者もこの牙にかけたことがある。
「もうしばらくは、ブローノ・ブチャラティの名を探ろうとする人間は……出ていなかったのに……」
命をドブに捨てるようなマネをする人間がまだこの街にいたのだ。苦々しく思う。たまに現れる、恐怖に耐性を持つ人間を。ようやく組織も落ち着き、孤児院や病院も今はうさんくさいギャングとしてではなく、街を司る組織の一つとしてパッショーネからの寄付を受け取ってくれるようになった。もちろん、ギャングからの寄付を受け取らないところもあった。そういうところには、ギャングの稼ぎとしてではなく、在宅でもできる小さな商売で稼いだ、ぼくのポケットマネーで、ブローノ・ブチャラティの名前を借りて寄付をしていた。
それまでの間、ぼくは彼への尊敬と、彼の夢を叶えるという覚悟の証として彼の名を使って寄付を続けていたのだ。きっとブチャラティが生きていたならばきっとそうする、そう思っていた。
本当の親を知っている子も、知らない子も、親を亡くして悲しみに暮れていたけれど、何の見返りもなしに育ててくれた『見えない父親』に感謝した。孤児院を出た子どもたちがそんな『見えない父親』あこがれて努力し、警察や看護士、消防士など街を守る職や、銀行員や政治家という淀んだ街の根本を変えようとする孤児たちも現れた。
決して見返りを受け取らない『見えない父親』に対する感謝を街の人々に向けようとする、そんなやさしいサイクルがいつの間にか生まれた。ぼくはそれを、ブチャラティに見せてあげたかった。彼が見たかった光景はきっと、これだったはずだ。
彼がなによりも憎んだ麻薬も取引を減らすことができた。完全に絶ってしまえば、中毒患者が街の外と取引をするようになる。そうなればこの美味しい利益を与えてくれるこの街をよそのマフィアやギャングが狙うようになる。そうなれば街が危なくなる。自然と彼が愛した護衛チームの仕事が増えていった。
このネアポリスには平和を与えなければ。ぼくはその一心で働いてきた。そして街もそれに応えてくれた……なのに今さらまた、この街を乱そうとするものが現れるなんて……。
そっと星形の痣のある場所に触れる。
「……これが引力……そういうことでしょうか?ブチャラティ……」
夜の街を映す窓には金髪の巻き毛のロマンチストが、あの時のブチャラティと同じような潤んだ瞳をしているのを見て、思わず笑ってしまう。
このホテルに仮の住まいを構えた『見えないボス』。それをかぎつけた新聞記者が最上階のスウィートルームに頼みもしない新聞を宅配してくれた。そのタブロイド紙には、名刺が挟まれていた。
パンナコッタ・フーゴ……とてもなつかしい名前だった。
第二章 紫の煙
2010/××/×× 新聞社
パソコンに記事を打ち込み、タバコをくゆらせながら最後の推敲。ネアポリス中で一番情報が早く正確。しかし、たった数面の記事のために膨大な金額を支払わないと読めない新聞がある。
ありがたいことに、その少ない情報量でもそれだけの金額を出していいと思わせるだけの何かがある新聞なのだという。それが我が社の新聞だ。
発行が早いものの不定期、数面しかないのは許していただきたいところだ。何せ我が社は記者が少ないのだ。そのかわり記者の何倍もいる情報提供者のおかげで、情報の早さと正確さは保証できる。株の動きから物品の取引情報、新商品の開発状況等の他に人気なのは、お偉いさまのスキャンダル。
短気は損気という。おかげでオレは大学進学への道を絶たれてしまった。しかし、その短気のおかげで今はこうやって金を稼げるようになっていた。ギャングたちの情報網と、この暴力的な性格のおかげで誰よりもこのネアポリスの闇に詳しい人間になった。
パンナコッタ・フーゴはブローノ・ブチャラティと別れた後、しばらくは一般市民に紛れておとなしく生活をしていた。ボスから暗殺命令でも出されて狩の対象にでもされない限りは、ずっとこうして穴にでもこもっていようと思っていた。
ブチャラティは裏切り者の自分から離れれば、組織から狙われないだろうと思っていたようだが、そう簡単に行くわけがない。組織の裏切り者を最後までみていたのはオレで、そいつが接触をとる可能性が高いのも、もちろんオレだ。組織から裏切り者だと思われても仕方がない位置にいる。下手に動く方がまずい。
だけど、彼を恨んではいない。彼が残してくれていた人脈があるから、一般人にも簡単にとけ込めたし、今もその人脈を利用して一旗あげているのだから。
しかし、ブチャラティはもう、オレに接触をとることはないだろう。あの人はそういう人だ。このままオレがネアポリスの一般市民に馴染めればと思っているに違いない。……この間も暴力騒動を起こして一軒店を出入り禁止にされたところだけど。
しかし、ネアポリスを外れたブチャラティらとともに状況は大きく変わっていく。ローマで大惨事が起こったのだ。大勢の人間が突然ボロボロと崩れさり、その姿もとどめぬほどの塵と化して死ぬというものだった。大規模な地盤沈下も確認されている。ローマでの異変に皆が戦慄したが、その騒動もびっくりするほど早く収まった。
「スタンド攻撃と見て間違いなさそうだな」
暇そうな人間を捕まえて丁寧に頼み込んでローマまでご足労願い、その時の砕け散った遺体の粉を回収させた。丁寧に調べあげたが、菌が定着した痕跡なんかを見つけたものの、どれだけ調べてももう、生物の気配はなかった。
念のためにローマにやったチンピラも調べあげたけれど、オレのかんしゃくで受けた傷以外は体の不調は訴えていない。
スタンド攻撃でほぼ間違いない。使役者が死んだからスタンドが消滅したのだ。ローマでの事件は広範囲のスタンド攻撃だったのだろう。ボスが隠していた駒だ、よっぽどの異常者のスタンドだったのだろう。オレの能力、パープル・ヘイズにも似ているが、その範囲の広さと容赦のなさには負ける。
その後もなぜか会う度に身体のどこかの骨を折り、オレに対して腰が低くなっていくチンピラたちを使って調べさせる。護衛チームの写真を見せ、特徴を丁寧に伝えてローマ中を調査させた。彼らは目立つからきっとすぐに見つかると思っていた。
その自信に満ちた姿が、その内面からあふれ出る……魂とでもいうようなものが……彼らを輝かせているから。
「やっぱりですか。行かなくてよかった……こんな面倒に巻き込まれずに済んで……」
でも、ローマの状況を調べた記事をいつまでも始末できずにいた。こんなオカルト的な記事、お金にもならないのに……。
「……まさか、悔しいと思っているのかな……」
今でも思い出す。遠ざかるナランチャの声を。
「勇気を出せずに……あの場所で立ち止まってしまったことを……」
そして、心配しているのかもしれない。彼らのことを。
キーを打つ手を止めて背伸びをすると、デスクチェアがギシッときしむ。背後に気配を感じて、ゆっくりと振り向いた。
「ようこそ、黒騎士……本当に、深夜に現れるんだな……ちょうど今次の新聞記事を書き終えたところだよ……時間はある?ゆっくり話がしたいんだけど」
なぜ……夜なのだろう。薄暗がりのオフィスに太陽の光を紡いだような金髪がなびいている。オレが最後に見た姿よりはずいぶんと大きくなっていた。ひどくたくましく、威厳をもち、その夕暮れの海のように黄金に輝く瞳は哀しみに満ちていた……。
「予想はしていたよ。黒騎士は君だろうなと……ジョルノ、お久しぶりです……」
ぼくは立ち上がって礼をする。背筋がゾクゾクしていた。この黒騎士と噂される男は噂通り音もなく現れ、そしてただ真っ黒なスーツをなびかせて、微動だにもせずに、こちらを見つめていた……。
「十一年ぶりですね、フーゴさん……」
その瞳に浮かんだ哀しみをオレはよく覚えている。あの凛とした十五歳の少年は今、目の前でブチャラティのあの静かで冷たい悲哀をまとって現れた。
「オレを始末しにきたんですね?」
ジョルノは少し弱気に目をそらした。なんだかそれが少しだけうれしい。彼はまだオレのことを仲間だと思ってくれている証拠だ。
「返答次第では……そうなるかも。それより、ぼくに用事ですか?」
名刺を胸元から取り出し、僕が確認したのを見届けると、またスッとポケットへ戻す。
「……パッショーネのボスにお会いしたい」
ジョルノは金色の目をじっとこちらに向けるだけだ。
「あなたのボス、ブローノ・ブチャラティに……」
2001/04/×× フーゴの仮屋
紙を広げ、まとめた情報を書き散らしたカードを張り付けていく。一人で行うさみしい会議だ。護衛チームのみんなと決別した後は別行動でボスのことを調べていた。
このネアポリスでの最高権力である組織に逆らう愚かな彼らのことなんて、本当なら気にする必要はなかった。
でも日常生活をおくっているだけでも感じてしまうのだ。真実を知っているものだけが感じる『消し飛んだ三秒』の違和感を。そのたびに気が気でなくなった。その頻度が増したことで、彼らがボスと戦っていることを知る。
そのたびに胸が痛んだ。じっとしていられなくなった。情報屋を生業にしているやつらを半壊させ、命の代償に情報を提供してもらい、個人的にボスの正体を探った。そこからこのアマチュア新聞業もはじめてみたというわけだ。
そんなある日、新聞の一面に乗ったローマの悲報。その日から、三秒が消し飛ぶ気配は消え、ボスの死亡が噂され、気づけばファントムのような黒騎士を手下にした『見えないボス』が現れたと聞いた。その瞬間、オレは気づいた。
--彼らから、完全に取り残されてしまったと。
もう二度と彼らの物語と自分は交わることがないのだと。
彼らとの記憶が毎日のように夢に出た。無性に沸き立つ後悔に吐き気をもよおした。ローマをすぐに調べさせた。そこには確かに彼らをみたという人物が何人もあり、彼らを抹殺しようとしたボスの親衛隊によりローマがひどい有様になったことも確認した。
そこから先、全ての足跡が消えたのだ。
新聞で稼いだ大金を湯水のように払って彼らを探した。しかし、誰一人見つからなかった。ジョルノ、あなたはわかる。まだ顔もそう知られていない新人だ。ブチャラティ……彼もギャングの幹部になった男だが、彼のスティッキィー・フィンガーズを使えば尾行も簡単にまけるだろう。ミスタは、彼は足取りを一度見失うと難しいかもしれない。暗殺が得意なのだオレの手下が近づいたらすぐに気づくだろうし、そこらへんのチンピラで敵うわけながい。
しかし、一番すぐにボロを出すだろうと期待していたナランチャ。なぜか彼の足取りでさえつかめなかった。オレの中のプライドが崩壊しそうになった。置いてけぼりにされているという状況が心を不安でいっぱいにした。なんでそんな風になるのか、わからなかった。ただ焦り、情報を一時でさえ逃すものかと眠りも浅くなった。
そんな時、孤児院に多額の寄付がされたという情報を手に入れた。このネアポリスにそんな金持ちがいたのかと不思議に思ったから調べさせてみれば、その差出人がなんと……ブローノ・ブチャラティ。思わず小躍りした。政治関連のお客も増えていたので偶然拾えた情報だった。
しかし、それでもやはり足取りはつかめない。使っていた情報屋たちも、深くまで踏み入ると干からびた死体になって見つかった。謎の大富豪、ブローノ・ブチャラティの正体はつかめない。一番あやしいのは、ほぼ同時期に現れた『見えないボス』の方だろう。
ブチャラティのことを調べさせた情報屋たちが干からびた姿で見つかったのは、生命力を操るジョルノの能力を思わせる。ジョルノとブチャラティの間にはオレたちの間にはない、なんらかの関係があることは薄々気づいていた。ブチャラティのために相手を始末する忠実なる『黒騎士』になったとしてもおかしくはない。
新しいボスが現れた瞬間、なによりも先に麻薬ルートの縮小、そしてそれにより他の街からやってくるであろう売人たちを始末するために、護衛チームに力が入れられるようになった。
これはどう考えても、ブチャラティのやり方にしか思えなかった。しかし、それにしても不気味なのは『黒騎士』の存在だった。いくらパッショーネを平定させるためとはいえ、ブチャラティが右腕としてこんな見せしめのような方法を使うだろうか?なぜ、ミスタを使って始末しない?
「生命エネルギーを限界まで注ぎ込み、枯れ果てさせる……ゴールド・エクスペリエンス……か?」
それが何か重要な位置にある?その予想は遠くないはずだ。
情報屋たちの標的を変えさせた。まずはあの目立つであろうあの美しい金の巻き毛の持ち主、痕跡を残しやすい能力の持ち主を探ろう。不可思議な事件が起きた場所を探れば、きっとすぐに当たるに違いない……そう読んでいたが、その推測も外れてしまう。
「ボス……その……ジョルノ・ジョバァーナってやつの墓が見つかりました……」
オレのかんしゃくを恐れて、おずおずと言う情報屋の手に大量の札束を握らせ、徹夜で目を血走らせながら車に乗った。ようやく、ようやく彼らの足取りをつかめる……。
ところが、その墓でまた謎が浮上する。墓守に訪ねたのだ。ここによく来る参拝者の髪色を。オレは夜のように真っ黒な、女性を思わせるあのおかっぱ髪を想像していたが……。墓守は言う。美しい金髪の巻き毛の少年だと。
「そんなわけはない!なんでここにジョルノ・ジョバァーナの墓があるというのに……!!」
墓守の頭は、オレの拳で陥没していた。助けをこう悲鳴にようやく、我に返った。
「……ハ、ハハ……そうか……でもようやく足取りをつかめたと言うわけだ……謎は残っているが、もう可能性はゼロじゃない……」
血反吐をまき散らしながらわめき、石畳を指でひっつかんで獣のように四つん這いになって逃げる墓守に向かって情報提供料と治療費として金をまき散らし……墓場を去った。
そして……ようやく今、ジョルノ・ジョバァーナ……あんたを目の前にしている。
2011/03/×× 新聞社
開いた窓から風が吹き込み、カーテンがなびいた。
「フーゴさん、あなたの狙いは……なんですか?」
目に忠告の色を浮かべてにらみ据えた。パッショーネの解体だろうか、それともブチャラティの名を汚し、この街の子どもたちに絶望を与えることか。しかし、彼はまだわかっていない。ブチャラティが死んだということが。ぼくが彼の探る『見えないボス』だということにも。
「……ただ、知りたかっただけさ」
フーゴはフッと表情を和らげる。先ほどまで血走っていた目にも勢いが消えた。
「オレはどうやら知らないって言うことが、何よりも耐えがたいみたいでね……」
彼の目からは嘘は感じられないし、この狭い部屋でスタンドを呼べばぼくを殺せるだろうにそれもしない。本当の言葉なのかもしれない。高い頭脳を持つゆえの悩みなのだろう。
「ブチャラティの代わりに全てを話してもかまいません。ぼくは彼の代弁者なのでね。ですがそれを記事にされては困るんです」
フーゴは賢い。だからほんの少しの情報提供で推理してくる可能性がある。あっと言う間に組織の大事に踏み行ってくるかもしれない。だけどぼくは、この人は絶対に……食べたくない。
どこかで今も、パープル・ヘイズがぼくを見ているかもしれない。しかし、吸血鬼になってしまった今、ぼくにはもうパープル・ヘイズの姿をとらえることはできない。スタンドが見えないことを気取られてはいけない。
フーゴはぼくよりも先に緊張を解き、来客用のソファへと向かって歩く。ぼくに向かって席を勧めてくれた。
「取引がしたいんだ。望みはただそれだけにしよう」
そういう彼の言葉を信じて、ぼくはソファに座った。フーゴも続いて目の前のソファに座る。
「すまないね。急な来客でまともなお茶も用意できていないんだ」
「……気にしないで。のどは渇いていない」
少し緊張感が解けたのか、フーゴの表情がやわらかくなった気がした。それがうれしくて、少し口の端が持ち上がった。
「ジョルノ、あんたが一番知りたいと思う情報を必ず仕入れてみせる。どんな無茶な依頼でもかまわない。ただし、そのかわりオレが離れた後ローマでなにが起こったのか、パッショーネはどうなったのかを教えてもらいたい」
ぼくは思考を巡らせる。今一番知りたいこと、それは……ぼくの父のこと。ぼくの『運命』。
「フーゴ、人を捜してもらいたいんだけど……あまり情報がないんだ十一年前ただ一度だけ出会った人物だし、知っているのは外見と名前くらいで……」
なぜか今、彼に会うべきだと思っていた。
「それだけわかっていれば充分さ、生きてさえいれば出会いの場ももうけよう」
「ありがとう、フーゴ……そのかわり、君が護衛チームを離れてから今日まで何があったか……話をするから……」
彼ならきっと信頼できる。ブチャラティの影を追って、ここまできてくれた彼なら……。ブチャラティが言う『運命』が彼を導いたというのなら……。
「ジョルノ、なんだか変わったよね……少しだけ、その、雰囲気がブチャラティに似ている気がする」
ぼくはあわてて顔を真っ赤にした。
「そ、そんなわけないでしょう!?」
ああ、こんなにも深くロマンチストに染まってしまったか……。
「ブチャラティは元気ですか?」
舞い上がった気持ちがすぐに失せた。
「……驚かないでください。ブチャラティは……死にました。今、言えるのはこれだけです」
あまり、彼の死を……言葉にしたくない。
2001/04/×× とある一夜
ブチャラティは口づけが終わると学制服の襟部分を後ろに引いて、またじっと星形の痣を見ていた。何か言いたげにしているが、まだ呼吸が整わないために、声が出ない様子だった。
ぼくは何度もブチャラティの体に自分の腰を打ちつけては、うっとりとその耳に舌をはわせる。
「んっ……あっ……!」
ビクンっとふるえて、ブチャラティのあげたしぶきがぼくの学制服を濡らした。彼が放った瞬間、彼の体内に埋められていたぼくの陰茎を、彼の体が強くしぼりあげる。
「ああ……あ……かわいいですよ……ブチャラティ……耳……いいんですか?」
「ひゃ……め……ぅっ……」
そろそろ限界がきそうだ。強く壁に彼の体を押しつけ、グッグッと斜め上に突いていく。力をなくした体がしなだれて、ゆがんだ筋肉のラインもいやらしい。
「なんて声……出すんですか……」
「あぁ……っぅ……」
そのまま恥いるように小さくなった彼の体を抱きしめるようにして、彼の体の中に、ぼくの劣情を吐き出した。持ち上げた彼の足がビクッビクッとけいれんする。
「ブチャラティ……あっ……んっ……」
おずおずとぼくの肩に腕を回したブチャラティは、真っ赤になって目を閉じてうつむいたままだ。もっと恥ずかしくしてやろうと彼のほほに耳に口づける。
「ジョルノぉ……ジョル……ゃめ……っ……」
全部出し切った陰茎をズルリと抜き取ると、ブチャラティの中からあふれでたぼくの精液がベッドのシーツを濡らした。
「っひ……っ……っぅ……」
あんまり苦しそうにしているから、彼の呼吸が楽になるように息でも吹き込んでみようかと、そっと唾液でしめったくちびるをふさぐ。ブチャラティは抵抗するように首をかしげ、呼吸を整えようとして嫌がるようにみじろいだ。ぼくの腕から逃れようとしたが、合わさった身体をすりつけるようにすると、小さくうわずった声を出し、ぶるりとふるえて大人しくなる。
何度も咥内をむさぼるように舌をすり合わせ、くちびるの端からこぼれ落ちた唾液がぬらりと光った。ぼくとブチャラティの間に透明の糸がつぅっと垂れ下がると、滴の重みにぷっつりと切れて消えてしまう。
しばらく抱き合ったまま、額をあわせてじっとお互いの様子を観察する。全裸の彼の体と、着込んだぼくの姿がなんだか滑稽だった。
呼吸が落ち着いてきた頃、額をすりあわせるようにしてぼくは言う。
「本当、マグロですね」
ブチャラティは、ああ驚いた、という顔で言う。
「……中学生の使う……言葉じゃあ……ないな……」
口元を拭うでもなく、快楽と息苦しさに潤んだ瞳でこちらをじっとにらむように見つめる。そんなに艶っぽくにらまれても、いつもの説得力がない。
ベッドの上で全裸のブチャラティを壁に追いつめるようにして近づいた。どうやら少しいじわるくされるのが好みのようで、困ったような顔をしながらも下半身が反応してしまう姿がかわいらしいと思った。
「もう少し強めに抵抗したらどうです。おもしろくないですよ、ブチャラティ……おかげで簡単に脱がされちゃって……」
そっと汗で張り付いた黒髪の一束をつかんで払ってあげた。しっとりと濡れた黒髪の艶は妙に色っぽいと思う。いつもは凛々しく引き結ばれたくちびるも、半開きになってずっとあえぐように呼吸している。こうなってしまえばぼくのお兄さんのようだった彼も台無しだった。
「……ンッ……ゴホッ……あの定期入れに……入っていた写真は、おまえの……父さんの写真か?」
いつの間にか学制服のポケットからこぼれ落ちたのだろう、定期入れが開いて落ちていた。ぼくは思わず顔を真っ赤にした。
「な、ないしょですよ?いい年して父親の写真を定期入れに入れてるとか、まるで子どもじゃあないですか」
「……っは……あ……こ、子どもじゃあないか……おまえは……」
弱々しくほほえみながら、ブチャラティがぼくの頭をやさしく撫でる。
「その子どもに無抵抗に好き勝手されたあなたに、言われたくありません……」
そのままずるりと倒れ込み、二人ベッドの上に倒れ込む。ぼくはそのままだらしなく腕を伸ばして定期入れをつかんだ。
「それを持っているのにも理由が……あるんだろう?」
ブチャラティも定期入れをつかんで、二人で写真を見た。
鍛えられたたくましい背中をこちらに向けているのは、燃えるような黄金の髪の男。顔はこちらに向けられているが、深い闇にその表情は隠されていた。一番印象に残るのはその左肩に刻まれた星形の痣。
何もかもが謎だが、写真からも圧倒的に伝わってくる迫力は……ただ者でないことがわかっていた。
「……ジョルノの、星と同じだ……」
ぼくの左肩を人差し指でぐるりといじる。
「きゅ……急にそんなところ……いじらないでください……」
ブチャラティはじぃっとぼくの目を、その深海の色をたたえたような目で見つめる。ずっとずっと、奥深くを探るようにして。
「おまえと、父さんの絆なのだな……」
そういってブチャラティにほほえまれては……悪い気はしないけれど、きっと彼にはぼくの『運命』が見えている。ぼくもその瞳に映った運命を見ようと見つめ返した。
先に恥ずかしそうに視線を逸らしたのはブチャラティだった。ぼくは笑う。勝負がつかないことを知っているから、先に折れてくれたのだ。
「……この写真は、突然学校にやってきた、変わった神父にいただきましてね……あれが僕の父親だと言って、この写真を置いていきました……」
「同じ金髪だけど、父親の方が少し黄色が強いかもしれないな……」
そういってブチャラティは三つ編みをもてあそんだ。
少し二人とも、疲れて感傷的になっている。彼も噂で知っているはずだ。僕は本当の父に一度も会ったことがないことを。二人目の父の暴力から逃れるようにしてギャング生活をし、そのかたわらでも、生きるために学ぶことをやめなかったことを。
「ぼくは自分で星形の痣を確かめたことがないし、写真はあるけれど、はっきり写っていないから、この男の顔もわからない……もしかしたらぜんぜん別人かも。ぼくは、あの神父にからかわれただけなのかも」
そう言って笑うと、ブチャラティは悲しそうな表情を浮かべた。なんだかそれが意外だった。
「そもそもぼくは黒髪だったし。もし本当にこれが父親の写真なら……その神父はちゃんと映った写真を持ってくるはず……そもそもあの神父自体があやしい人間で……」
人差し指がそっと、くちびるにおしあてられる。
「これだけヒントがあるのに、なぜ、星を探さない?」
「……っ……」
その言葉にちょっとムッとしてブチャラティをにらみつける。でもなぜか言葉が上手にでてこない。ブチャラティのその表情はとても無邪気で、疑問以外のなんの表情もうかがえない。
「ぼくにはもう父がいるし……さ、探さなくてもいいと思ったんですよ。あなたに話したでしょう?ぼくを救ってくれたギャングの事を……彼さえいればぼくは……大丈夫だから……」
人には三人の父親が与えられる。産みの父である肉の父と、名付けてくれた聖霊の父、そして、天からぼくたちを見守る父。
「自分の血統を知ることは、自分の運命を知ることでもある」
これだけ言ってもブチャラティは少し責めてくる。少しうんざりしたような表情を浮かべると、首を横に振られた。運命に傾倒したがるのはブチャラティの悪いクセだ。
「ぼくはロマンチストじゃあない。どこかにいる父親になんて興味はない。今を生きることで精一杯だ!それに……大体、ぼくを心配しているというのなら、父親の方からぼくをみつけに来るべきではないですか!」
そうだ、あんな神父を寄越したくせに、それから先、音沙汰がないじゃないか。
ブチャラティは小さく首を傾げて考え込んだ。
「確かにジョルノが言うとおりだ。子どもからではなく、親から探すのが当然だろうな」
目が細められるたびにその海のような瞳の色を深め、じっと僕を見つめた。息が詰まりそうだった。その分析しようとするようなブチャラティの視線は苦手だ……。
「ジョルノ、おまえは本当の父を知るのがこわいんじゃないか?」
ぼくはあわてて答える。
「名前はディオ・ブランドー。エジプトにすんでいたが、もうすでに死んでいる……その神父から遺骨だって見せられた。脚の骨の一部だ……たぶん右の大腿骨。それだけ知っていれば十分でしょう?」
また人差し指が僕のくちびるをついた。
「おまえのそういうところが、オレには不思議で仕方がない。なぜ自分の血縁をもっと真剣に求めようとしない?」
だめだ、さっきまでこちらが押していたのに、またブチャラティに主導権を握らせてしまった。
「だけどジョルノ、そういう現実主義的なところがおまえなのかな……とも思う……」
人差し指は、ようやくくちびるから離れると、そっとその先を自分のくちびるへと持っていく。
「きっと、曇りでも見える星を持っているから不安にはならないんだ……。ジョルノには、常にそこに道しるべがある」
そう言って、ブチャラティはぼくの星形の痣をいじった。
「……ぼくにはもう、何も見えなくなった……」
ブチャラティの見開かれた瞳は少し悲しく、どこか恐ろしい。
「トリッシュ……彼女には星が見えている。血族の『運命』という星が。彼女には乗り越えなければならないものがある」
「あ、あなたにだってあるでしょう……このネアポリスから麻薬を……」
「ああ、だからオレは命を張る。そして行動することが何一つできなくなったその時は『運命』にゆだねる。オレにまだ使命があるならば死なないはずだから」
ゾクリと震えた。彼の中の諦観とも言えるその意見は、ブチャラティらいからぬと思ってしまった。
「僕はあなたのそういうところが不思議で仕方がないんです。そんなに……与えられた運命が大事ですか?」
運命は切り開ける。これが僕の結論だ。親から養われることは完全にあきらめ、自ら生活するために生きるために必要な分だけ他人から拝借する術を身につけた。
知りたいと思えば図書館に行ったし、必要とあれば本を買った。新聞をむさぼり読んだ……。僕が今生きているのは親のおかげなんかじゃない。神様のおかげなんかじゃない。ぼくが自身で、運命を切り開いてきたからだ。
「……ジョルノ、オレはおまえに会う少し前、不思議な経験をしたんだ」
そっと伸ばされたブチャラティの少し体温の高い手が、ぼくのほほを包み込んだ。マンマの言うことをようくお聞き、というわけだ。
「……オレの死を刻み込んだ石が追ってきた。神出鬼没なその石はとてもしつこく追ってきた」
小さくブチャラティのくちびるが動く。
「本当だったらオレは、そこで死ぬべきだったかもしれない」
ブチャラティの表情はひどく真剣だった。
「だが、命をかけてまで、オレを救ってくれた人間がいた……ミスタだ。彼はその石を抱え込んだまま、ビルの七階から飛び降りた……ミスタが言うには、その石に触れていればオレは……安楽死していたらしい」
ぼくはその真剣な話の主役がミスタだということに驚き、思わず吹き出しそうになった。しかし、ブチャラティに対してとても忠実な彼なら、それくらいしてもおかしくはない。
「その石には運命が刻まれているという……つまりオレは、あの石と同じように体を切り裂かれ、血を吐いて死ぬんだという」
ブチャラティはおびえもせずにそう言った。
「オレは生かされているんだと知った」
その不思議な経験は、ブチャラティの中に大きな人生観を生んだのだ。そして、誰よりも真剣に『運命』というものを信じるようになり、ぼくが自分で自分を生かしていると思うように、自分を生かしてくれている『運命』というものに忠実に生きる騎士になったのだ。
「もしかすると、命をかけてまでオレを生かそうとする、そういう人間に会えなければ、オレはきっと死んでいたと思うんだ」
出会いは、引力……。いつかブチャラティが行っていた言葉。
「だからオレは『運命』を信じるし、星を見上げる。だけどジョルノ、おまえがにらみ据えるのはどこまで続くともしれない闇だ。果て無き荒野かもしれないが……おまえはただ地上を見据える」
そうやって『運命』という言葉を素直に受け入れ、そうやって美しくほほえむことができるあなたが不思議で仕方がない……。相手はおそろしく残酷なんだ。わずか一才の少年を、平気で闇に置き去りにするような母に与えるのだ。だけど、その儚さが……どうしようもなく心を揺り動かす。
「ジョルノ、おまえは……オレみたいに道を探す人間じゃない。自分の歩く場所そのものが道なんだ、きっと……」
それがジョルノ、おまえの強さだ……そうつぶやいて、そっとおでこをぶつけた。ぼくの目からは涙がこぼれ落ちそうになった。彼とぼくの歩く道はとてもよく似ているけれど、実はおそろしいほど離れている道なのかもしれない。そう思った瞬間、ダダをこねたくなった。
「引力はオレとおまえを引き合わせてくれた。おまえに出会わなければオレはきっと……上を見上げてばかりで、道の見つけ方すら知らなかった」
納得しちゃいけないかもしれない。でも、それでもぼくは、そんなブチャラティの姿から学んだことがある。ぼくも、ブチャラティのほほに手を触れた。
「ぼくだって……あなたと出会ってから……空を見上げると、星があることを知った……」
本の中の情報だけは知っていた。でも、ぼくは見上げることをしなかった。でも、ブチャラティが空を見上げるからぼくも……見上げることを知った。……そう素直に思ったことを言うと、ブチャラティはうれしそうに目を閉じてほほを赤らめた。
「オレは確かにマグロかもしれないな」
フッフッフッ……とブチャラティが笑う。
「おまえは自分の道を自ら求め、歩む。オレはただ、神からの運命という命令を待つだけなんだから……」
2006/06/×× 新聞社の一室
フーゴは思いのほか早く、探し人を見つけだしてくれた。エンリコ・プッチという黒人神父だ。彼は五年前、父の写真をぼきうに預け、息子のぼくに遺骨を見せて、これだけはどうしても必要なのだと、そのまま持ち去った。
その情報料として、ローマであった一切を語った時、フーゴの目からは涙がいくつもしたたり落ちた。耐えようとしたが、無理だったようだ。
そして、そんなフーゴにもう少しわがままな以来をした。できればコンタクトをとりたいのだ、と。しかし、なんでも、神父自身がぼくを探していたらしい。だからこそスムーズに事は運んだ。ブチャラティに言わせるならばこれはきっと『運命』なのかもしれない。
パッショーネの内情なんて大勢の命に関わるような情報と引き替えにしてはあまりに個人的な内容だったが……今のぼくにとってはとても大きな事件だった。
もちろん、なるべくなら信頼のできる部下にお願いしてもらい、ぼくが彼を探していることをおおやけにしてほしくないし、なぜ彼を探しているかの詮索は絶対しないと約束してもらった。
フーゴはパッショーネの内情を知るためならなんだってする、とこんな不思議な依頼でも請け負ってくれたのだ。
しかし、いざとなると緊張した。五年前にたった一度だけ出会った謎の神父。どういう服装で彼に会えばいいのだろう?どんな顔をすれば?そもそも、何を話せば?普段通りお気に入りの店で仕立ててもらったスーツに身を包み、隠れ家のホテルの一室を待ち合わせ場所に決めた。ぼくは少しソワソワしながら神父の到着を待った。
やがてコン、コンっとノックが鳴り響いた。
「なかなか厳重な警備だ。五年たって、君を取り囲む環境は大きく変わったようだ」
そう、あの時彼と出会ったのは、一般的な中学の寮だった。ところが今は高級ホテルの一室……しかも中にいるほとんどの人間は組織の部下たち、というわけだ。
「ええ、詳しくはお話できませんが……」
そう言って、ぼくも神父に礼をして席を勧めようとしたが、神父はじっとぼくの顔を見つめるばかりだった。あまりに真剣にこちらを見つめるもので、緊張が走った。
「……君自身、大きな変化があったようだ」
背の高い黒人神父は頭にかぶった黒い帽子を脱いで、ほほえみながら礼を返した。彼の表情はどことなく哀愁がある。しかし、その瞳は何か信念に光輝いていた。
その瞳は、常にはるか遠くを見据えているようで、その先に輝く何者かをとらえていた。なんとなく、ブチャラティを彷彿とさせた。彼もきっと神に対して敬虔な人間なのだろう。
「以前よりもあなたはDIOに似てきた……」
ソファーに腰掛け、ぼくも腰掛けるのを確認してから足を組み、組んだ手に顎を乗せた。じっとぼくを見つめている。
「うれしい。DIOの息子自らがぼくを探してくれただなんて」
「……はい、ぼくの父、DIOについて聞かせてはいただけないでしょうか……」
覚悟を決めるのに五年かかった。今までずっと逃げ続けていた。肩にある星の意味を知ることに。この吸血鬼という呪われた血の正体を知ることに。
「君は、吸血鬼なのか?」
部屋は昼だというのに薄暗く、点いているのは電灯だ。誰だっておかしく思うだろうが、父を知る彼ならばその理由を見抜いてくれると信じていた。話が早く進んでいい。ぼくはうなずいた。
「ぼくはいままでDIOの息子を三人見つけることができたが……その誰もが普通の人間として暮らしていた……」
少し神父は興奮気味だった。
「やはりぼくは、間違いなく『天国』へと押し上げられているんだ……」
「……その、あなたは父とどういう関係だったのですか?ぼくのほかにも……父には息子がいる?」
この神父はアメリカ中を旅しているようだとフーゴから聞いてはいたが、もしかしてDIOの息子を見つけるというのが彼の旅の理由だったのだろうか。
「ええ、三人います。居場所は見つけたが、まだコンタクトはとっていないよ。まだ、その時じゃあない」
これで答えになっているかな?と、ちらりとぼくの方を見た。ただ、だまってうなずき返すと、夢見るように言葉を継げる。
「ぼくは彼の『友』だ。彼はぼくの崇拝を受け入れてくれた。そして彼は、ぼくを同じ高見へと引き上げようとしてくれた。ぼくと彼との関係を言うなら、神と神父、そのものでいいと思うよ」
そう言って彼は父との出会いを話してくれた。きっと五年前にも同じ話を聞いただろうが、あの時はすべての話を聞き流していた。だから何もかも新鮮に思えた。
教会の台座の下で寝そべる不思議な男につまづき、人との出会い『引力』を説かれ、生まれたときからねじくれて動かなかった左足を何事もない健康な足に変えるという奇跡を起こしたこと、そして人とのであい『引力』を説き、石の矢を授けてくれたことを語った。
「ぼくにとって彼は神だ。生きた神だ……姿を見せない神よりも確かな神。何度もぼくに奇跡を起こしてくれた。石の矢を、ぼくに託してくれた」
「……石の矢!?」
ぼくは思わず立ち上がりそうになった。
「これでいつか、私を思いだしてくれと言ってね。この矢はぼくにとって、人生で一番大きな転機に奇跡を起こしたんだ……彼は、どうしようもなくなったぼくの人生に、二度も奇跡を与えてくれたんだ」
「……あなたももしかして、スタンド能力者……なんですか?」
それを聞くと、プッチ神父は不思議そうにぼくを見た。
「君には、見えていないのか?」
ぼくは歯を食いしばった。バレてしまった。不注意にもこちらにスタンドが見えないことを知らせてしまった。相手の能力はいったいどういうものかもわからないのに、自ら弱点をさらしてしまった!
スタンドがぼくを抱えているのだろう、体が宙に浮いた。強く引きつけるようにするものだから、胸部に何かが当たる感触がある。腕のある位置からして、スタンドはぼくをじっと見つめているのだろう。腕に手を回して、まるでこれからワルツでも踊ろうとするように。
その時、突然激しい衝撃がぼくの胸を突いた。打撃に激しくせき込み、空中に目を凝らす。
「ぐぅうう!」
うめき声をあげたのは神父だった。なぜかぼくを攻撃したはずの神父手のから、血が滴り落ちていた。拳の肉は矢の形にえぐれ、神父はそれを見て目を輝かせた。
ぼくは目を伏せる。ぼくの胸ポケットには、あの石の矢をいつも入れていたのだ。いつでも仲間たちの意志を連れて歩いていた。仲間たちはまだ、ぼくに生きろと言っているのだ。
「ぼくは、勘違いをしていたかも知れない……。ぼくは、君がDIOを『天国』に連れていく鍵の一つにすぎないと思っていたが!」
ゆっくりとソファーの上におろされる。
「……『天国』……」
ぼんやりとスタンドがいるであろう方向を眺め、そして本体である神父に視線を移す。
「君は、父とは違う『天国』を見る『運命』なのかも知れない」
プッチ神父は傷ついた拳をうれしそうにながめていた。
「……君には、『友』があったろう?己の欲望のために生きるのでなく……常に周りのために生きるような……無欲な『友』が……」
彼の言葉に思い出したのは……ブチャラティだった。
ギャングスターになると決め、最初に必要だと思ったのは絶対の忠誠を誓う誠実とやさしさの人だった。麻薬をやっていた少年の腕を見て攻撃をためらったブチャラティを見た瞬間、パッショーネという腐り果てた組織の中でこの人以上の人物は見つからないだろうと思った。
「そして、君は一度スタンドを捨てたはずだ……スタンドというものを知っているから相手の能力にわざと身をゆだねる勇気を持っていた。すばらしい!そうか……『運命』を指し示す矢は……一つではなかったのか…!」
なんとなく、できるような気がしてプッチ神父の傷ついた拳に手を触れる。細胞を活性化させるイメージを強く思い浮かべる。
「……ゴールド・エクスペリエンス……」
その時、プッチ神父は輝く目を見開いた。
ぼくの目の前では、彼の拳の傷がみるみるふさがっていった。
「……あっ……」
あわてて神父の視線の先に振り返ったが……本当ならそこにあるはずの姿が……それでもぼくには見えなかった。
「神々しい……DIOのスタンドにも負けぬ……黄金のスタンド!」
「みっ見えたんですか!?」
ぼくは思わず神父の体を揺さぶった。
「間違いなくあなたはDIOの息子だ……知らず知らずのうちに、父と同じ道を歩んでいるんだな……」
神父の目が鋭くなる。
「……それがぼくの道の邪魔をするものならば、この場で君は命つきていたはずだ……だが、ここに矢があって、君は死ななかった。もう一つの『運命』がここにはある……ということか……」
そして、うれしそうにほほえんだ。
「DIOは言った。天国に向かうには『友』と一度己のスタンドを捨てる『勇気』が必要だと言った、そして、復活のために己のスタンドに『十四の言葉』を刻んだ。三十六の『罪人の命』を捧げ……十四の言葉を告げたとき……もう一度彼は復活すると言った」
ぼくは彼の言葉を胸に刻んだ。
「そうして、ぼくとともに『天国』へと上るのだと……」
リムジンを呼んで神父の目指す方へと送るように命令した。
去り際、彼はぼくの方を振り返っていった。
「アメリカにいっしょに来る気は……ないか?」
ぼくはその力強い目を見ながら首を横に振った。
「このネアポリスを守らなくては。ようやくあの人の望む街へと変わりつつある……それが今のぼくの生きがいなんだ」
「それは、あなたの『友』なのか?」
うなずいて見せた。友、というと少し語弊があるかもしれない。だが、彼はぼくにとって……最高の『友』に違いない。
「彼のおかげでギャングスターになるという夢を叶えることができた。だから……今度はぼくが彼が望んだ街をつくりたいんだ」
ギャングスターになりたいというぼくの点の夢をつなげ、未来へと託す線にしてくれた。五年たった今もギャングスターでいられるのは彼のおかげなのだ。だからぼくは……彼の名前を押し上げたい。少年だった僕を彼が押し上げてくれたように。
「……五年前よりその眼は野望に燃えている。その炎はあまりに青く静かだ……」
神父は胸に手を当てる。
「五年前よりも君はDIOに近づいた。ぼくは君の手を取りたいと思う。だが、運命の矢は分かたれていた」
神父は静かにほほえむ。
「神の加護を」
リムジンに乗り込む彼を見ながら、ぼくは呆然と『天国』について考えていた。
--またもや、ロマンチストにひどく毒されてしまったようだ。
「矢が示す、力の先……」
空を見上げる。星空にはぼくには読み解けぬ『運命』がいくつもの図形を描いている。
第三章 矢の向かう先
2011/03/×× ホテルの一室
トリッシュをうらやましがっていた過去を思い出す。あまりに真っ直ぐに己の血縁を求めることができた彼女には、一時であれ『運命』というものが目に見えていたのだろう。
生まれた時からすでに彼女は父親を知らなかった。それなのに彼女は血のつながりで父の魂を感じることができた。
しかし、父と出会って、何者から生まれたのかを知ると言うことは、同時に『呪われた運命』を受け入れることになった。それでも彼女は運命を力強く乗り越え、悪魔の血縁者としてではなく、今も強く自分の人生を生きている。
そんな運命を飛び越えた、強い女性から手紙が届いていた。
「バンビーノ・ブローノはお元気ですか?か」
なぜぼくに聞くのだろう。ぼくは彼と血のつながりはない。聖霊の父親というものの役割は、肉の親の代用で、確かに小さなブローノを養育する義務はあるかもしれない。でも、社会的に死んだも同然の人間にはどうすることもできないのだ。
ぼくは、この世に存在するだけで、ブローノへの義務を果たしているはずだ。名付け親という父が確かにこの世に存在していると知るだけで、人は生きる力を得ることができる。あのギャングが、ぼくにそうしてくれたように。
「きっと元気さ。ギャングのぼくなんかが、かわいいバンビーノに悪影響を及ぼさなければね……」
非情だと思うかも知れないが、ぼくは命を常に狙われるし、敬虔な神の使いの彼とは、住む世界の違う、非道徳の王なのだ。バンビーノ・ブローノはなにも知らずに平和に暮らすのが一番だ。
それに、十分な宝物は彼に与えた。彼は自分の名前に誇りを持っているはずだ。ブローノ・ブチャラティ、今では孤児院や学校、病院を利用したもので、その名前を知らぬ人間はいない。彼のおかげで命を救われ、知識を得ているのだから。
「……生きていたら……今年で十一歳でしょうか」
知らない間にもう、二十歳をすぎていた。今年の誕生日を迎えれば二十六。未だに組織の方向転換に異議を唱えるギャングたちはいるし、麻薬ルートを経ったぼくを憎んでいる奴らもいる。まだネアポリスはぼくの、ブチャラティの願う街にはほど遠い。
そうなるまではバンビーノ・ブローノには会う必要がないと思っていた。そもそもぼくがゴッドファーザーになっただなんて知れたら、彼の命まで危険にさらされる。
それに、ぼくは彼が本当にブチャラティの生まれ変わりだったらどうしよう、とおびえていた。彼が愛してくれた生命を与える力を失い、生命を奪う側になってしまったぼくなんて、彼に見られたくなかった。
笑える話だ。ぼくはいつの間にブッディストになったのだろう。輪廻転生なんてあるわけないとずっと思ってきたのに。
……ですよね?見えないブチャラティに語りかけながら、椅子の背もたれに身を預け、開けはなった窓から星空を見る。
「もうあなたの年を六つも越えましたよ……身長も大きくなった。ここにくれば、あなたをすっぽりとくるんであげられます」
見えもしない、彼のほほえみが見える気がして、思わず笑む。
「ようやくあなたにバカにされない大人になったつもりですが……いつまでもそんな高いところにいたら、どれだけ背が高くなったか、わかんないでしょうけどね……」
ぼくの頭に手を乗せようとする彼が居るような気がする。今でもぼくが甘えられる人は、あなたしかいない。ぼくを叱り、隣にいて、ともに歩もうとしてくれる人も……。ぼくは孤独だ。
机の上に置かれた数少ないブチャラティの写真を手にとる。ぼくの仕事を見守ってもらうために額の中にキチンと入れて、机の上に置いてある。
彼はいつまで経っても年をとらずに二十歳のままだった。ぼくは全力で生き、争いが耐えずともこのネアポリスを、ほかのどんな街よりも人々の心が燦然ときらめく土地に変えたつもりでいた。
「本当は胸を張ってもいいのかもしれない……おびえる必要もなんてないはずだ……だって相手ブチャラティだぞ」
あなたが幹部をしていたあの時代よりもはるかに護衛チームは大きくなり、街の賭博や飲食店、難民たちに開かれた職場で活躍している。孤児院も学校も病院も建物を新しくする余裕ができたし、公園に並ぶ失業者の数も減ってきた。ゴミを捨てても拾う人間が現れた……。古代の遺跡に敬意を払い、掃除をするご婦人も現れた。
収入はディアボロがボスだったころよりは少ないだろうが、街の心は驚くほど裕福になったと自慢に思っていた。
「……最近事務に追われてひきこもり続きだし……少しくらい散歩にでてみようかな」
時計を見れば夜の七時だった。さきほどまで五時だったような……。
「敵スタンドのおかげで経験したっけね。年をとると時間が経つのが早いって事。でも、最近は特にひどい気がする……まだ二十六なのに。吸血鬼になってから昼夜逆転しているせいでしょうか」
そんな頭の悪い独り言をしながらクローゼットに向かう。突然の思いつきに、少しご機嫌になってしまった。久しぶりに彼に会いに行こう、とっておきのスーツを着ていこう。そうでなければ、彼に笑われてしまうだろうから。
1
闇に紛れる黒色のスーツに身を包み、手には子どもたちへの土産の品としてクッキーやキャンディ、チョコレートをまるで宝石のようにきらめくリボンをつけて準備した。お菓子屋のおかみさんが、孤児院に持っていくといったら張り切ってくれたのだ。まるでもうクリスマスがやってきたようなお土産だ。そのせいでずいぶん時間がかかってしまったけれど。
もちろん、シスターに手渡すと喜んでくれた。
「ありがとうございます。シニョール……これはブローノへ?」
「いえ、もちろんこの孤児院の子どもたち全員へです」
シスターの深いしわを刻んだ顔が厳しくなる。
「あらうれしい。でも、少しくらい自分の子どもはひいきしてあげるべきですよ?特に十一年ぶりなのですから」
これがいいかしらね?と、うれしそうにチョコレートの包みを選ぶ。
「ブローノをお呼びしますから、せめて手渡していってあげてくださいな」
老齢のシスターはおだやかにほほえんで、ぼくにチョコの包みを手渡した。ぼくはどうしていいかわからずに思わず顔を赤くしてしまった。
「親が子に会いに来るのは当然です!もっと胸を張って!」
少ししかりつけるように彼女は言った。彼女はぼくの背中を押して孤児院の奥へ向かおうとしたが、あわてて断った。
「ほ、ほら見てください!時計……もう九時近いです……子どもたちはもう寝る時間でしょう?」
と、なんとか行動の素早い彼女を振りきって断った。
シスターはひどく残念そうな顔をしていたが、ようやくぼくを見送ってくれた。
「……ああ、かわいそうなブローノ……どれだけあなたを慕っているかご存知ないからそんなことを言えるんですわ……」
「ブ、ブローノが……?」
血のつながりのない名付け親とはいえ、彼にとって親と言えるのはただ一人、ぼくだけだった。それは知っている……だけど、それでも……。
「い、いや、というかシスター……ぼくが名付け親だって言うことを黙ってくれるのがお約束のはずですが……」
「ええ、もちろん約束は守っておりますよ?ブローノはあなたの名前も顔も知らない……でも、きっとあなたを父だと気づくでしょう」
シスターの意味深なほほえみと言葉に背中を押され、少しだけでいいから教会をのぞいてやってくれと言われた。孤児院の隣、小さくても美しい教会が、夜の闇に白く浮かび上がっていた。
ぼくはおそるおそる芝生を踏んで教会の入り口に向かい、中を覗いた。一番前の席に、黒い頭が小さくぽつりと見えた。懸命に何かを祈っているようだったので、ぼくはそのまま扉を閉めて歩きだした。
……しかし、こんな夜遅くまで、何を祈っているのだろう。
「気づくはずがない。彼はブチャラティとは別の人間だし、彼がぼくに会ったのは十一年前、目も開かぬ赤子だったんだ……」
そう、目も開かぬ頃。ぼくは彼の目が何色なのかも知らないのだから。
「そうそう簡単にブッディストに鞍替えはできませんよ」
ぼくは笑いながら石畳を踏んで街へと向かう。街路樹が案内するように、石畳の両脇に立っていた。
その瞬間、入り口の向こうから駆けてくる誰かがいた。ぼくはそのまま無視して歩いていると、突然背中に抱きつかれた。
「うわっ!!」
なんとかこける前に街路樹に手をついて難を逃れた。
「はぁ……はぁ……あ……っ……」
ぼくの腰にしがみついたまま動かない黒髪の少年は、下に顔を向けていて顔が見えなかった。力つきた少年の重さに思わず膝を曲げた。ぼくが逃げるのをあきらめたのが伝わって、ようやく少年から力が抜けた。
「待って……あなたが……あなたが……オレの……ゴッドファーザー?」
よほどの勢いで走ってきたのだろう、まだ荒い呼吸が収まらない。
「人違いだな」
ぼくはそう残酷に返した。しかし内心揺らいでいた。血のつながりが何らかの影響を与えるように、聖霊のつながりもまた、何らかの影響を与えるものなのだろうか……。背筋がぞわりとした。
「ぼくはただ、あの孤児院にお菓子を届けに来ただけだよ」
黒髪の少年はしがみつきながら、街灯に照らされて艶やぐ黒髪を横に振った。
「それともお菓子をおねだりしにきたのかな?」
しかたがないな、としゃがみこんで、ポケットからシスターに押しつけられたチョコレートを渡そうとしたが、少年は受け取ろうともせずに、ただギュっと拳を握ってぼくを見ているだけだった。
「オレにはわかる……あなたが……ぼくの……パーパだって!」
本当の父を失おうとも、本当の母を失おうとも人間は生きていける。悲しくても、心のどこかに精神的な支えさえできれば……強く生きられる。ぼくはただ、その手助けをしたかっただけだし、ぼくのことを知らない方が彼のためになる。それ以上は関わってはいけない、と表情を厳しくした。
「……ぼくのパーパだってぼくの心が言ってる!……シスターだって言ってた!ぼくのパーパは天使みたいにきれいな金髪の巻き毛してるって……」
しがみつかれたままで、どうしようもなくてその場に立ち止まる。白いワイシャツに黒のスラックス、きっちりとした真面目な学生なのだろう。その細い腕からもケンカもしたことのないように思える。
「君はいくつだ?僕は君が赤子の頃には、今の君とそう変わらぬ年齢なんだよ?子どもがそんな大役を引き受けるわけがないだろう」
笑ってチョコレートを差し出しても、少年は首を横に振る。
「いいえ……シスターはオレの洗礼式を覚えてるって……誰がゴッドファーザーか知っているもの!その日のこと、オレのために覚えていてくれて……オレがパーパと出会えるように毎日祈ってくれてて……」
スーツの裾を握ったまま少年は放そうとしない。
「ずっとオレも祈ってた……ゴッドファーザーに会いたいって……たった一日でいいからって……そしたら今日、はじめて神様が言ったんだ。パーパがいるぞ、追いかけろって……」
聞き分けのない少年に戸惑いながら、その頭を撫でる。やわらかい黒髪がさらさらと指の間を滑っていく。ようやく少年は涙で濡れた顔を上げた。
「神様がしゃべるわけ、ないだ……ろ……」
僕の心臓が跳ね上がった。その黒髪の下からのぞいたのは、あの深い海のような青い瞳。前髪はセンターで分けているが、髪は顎のラインに沿って真っ直ぐに切りそろえられていた。
そう、ずっと二十歳のままで止まっていた彼の……あの面影がそこにはあった。
赤子の頃はどんな目の色をしているのかすらわからなかった。ただ、ブチャラティの命日に出会った黒髪の子だったから『ブローノ』といたずらに名付けた。どこかにこの子が生きているというだけで、ネアポリスがもっと大事な街に思えるから……。もっと、彼の願いの願いを叶える覚悟をできるだろうと思ったから……。そんな、生き返りを信じるなんて事、ほんの冗談でしか思っていなかったのに……。
「聞いていたとおり……システィーナ礼拝堂の……天使にそっくり……」
ほほを赤らめ、涙でびしょ濡れになった顔でにっこりとほほえむ少年に心臓がまた飛び跳ねた。
「……シスターがね、私が忘れてしまう前に教えてあげましょうって……一度だけシスティーナ礼拝堂に連れていってくれたんだ……ちょうどあんな風な美しい、金色の巻き毛をした少年だったわ……って……」
しゃべりながら感極まったのか、ぽろぽろと涙をこぼし始めた。
「……だから……ぼくは君のゴッドファーザーじゃ……ない!人違い……だと……」
じっと見ていられずに少年から顔を逸らした。涙がほほを伝い落ちそうになったのをあわてて拭う。
「あなたが……ギャング……だから?」
グッとスーツを引く手の力が強くなる。この子ども侮れない……はずし忘れていたスーツの襟の紋章を目ざとく見つけてしまった。
「お話、ききたい……あなたのお話……たくさん聞きたい!一日だけでいいんだ!」
そっと、しゃくりあげる少年の方に両手をおいた。
「……わかった……わかりました。あなたのゴッドファーザーごっこをしてあげればいいんですね……」
少年はようやくスーツを握った手をはずす。
「……あなたの名前は?」
「……ブローノ……」
そっと手を握ろうとすると、ブローノの手は緊張にふるえていた。しかし、子どもの体温はとても、あたたかかった。
「オレ、ずっとこうしてパーパに手を握ってもらいたかったんだ」
「しかし困ったな、ぼく、まともに恋愛をしたこともないのに、もう子どもだなんて……」
すっとぼけるぼくにブローノは怒った顔で見上げた。見上げる彼の顔を見ていると、なんだか少しだけ、心の奥底で何かが満足するぼくがいた。彼は、ブチャラティではないし、性格だって似てもつかない。でも……なんだか、ずっと彼に見上げてほしかったという願望が満たされたような気がした。
「そういうパーパじゃないんだ……オレだってよくわかんないよ……。でも、あなたがパーパだってオレ、信じてる!だって神様が会わせてくれたんだもの!」
そう言ってほほえんだブローノを見て、心臓の奥底がこそばゆくなった。そうだ、ぼくだって幼い頃、ぼくを助け続けてくれたあのギャングを本当の父親だと信じて生き続けてきたじゃないか、と。
本当の父親が別にいることも、暴力を振るうあの新しい父もまた、法律的に本当の父親だということも知っていたのに……ぼくが本当に愛した父は、似ても似つかぬ、接点すらほとんどない、あのギャングの男だった。
ぼくは知らない間に……この少年に、あの時のギャングが与えてくれたものと同じ『希望』を与えていたのだった。
「……なんでだろう、君があんまりかわいいからかな……ぼく、ちょっとだけパーパ役でもいいかと思えてきた」
「……ねぇ、パーパ!パーパの名前は?」
ぼくはしばらく戸惑ったが……きちんと名乗ることにした。
「ジョルノ・ジョバァーナ」
「ジョルノ!ボン・ジョルノ!夜だけどあなたの髪はきらきら光ってる!太陽みたいに!」
ブローノはスキップをはじめる。
ぼくは思わぬ彼の言葉に、顔を真っ赤にして見つめるだけだった。しばらく呼吸を整えてから、ようやく言葉にする。
「……あなたの髪もすてきですよ……そう、夜の闇によくとけ込む……きれいな黒だ……」
夜の闇の中、月光で輝く清流のようにはずむ黒髪の下、ブローノはニッと笑って振り返る。
「おそろいだね!」
「……違いますよ。正反対だ。ほら、パーパ役には向いてない」
そう言って笑うと、ブローノはムキになって言う。
「そんなことないよ!朝がこないと夜がこない!朝と夜はひとつながりだもの。切っても切り離せないんだから!」
「むっ……まだそんな屁理屈をいいますか……」
「ジョルノだってしつこいぞ!いい加減認めろよ!」
ブローノが楽しそうに笑うから、ぼくも悔しいが、笑ってしまった。
そのまま夜の街を歩いてバルにつれていき、好きなジェラートを買い与えた。味は二人とも同じチョコレート味。まだ少し物足りなさそうだったのでブローノにはコルネットを与えて、ぼくはカッフェをいただいた。
「ねぇ、ジョルノってギャングの幹部なんでしょう?」
「いいえ?下っ端の下っ端です」
「うそだぁ!子どもだってバカにするなよ!ぼくだってネアポリスの子どもだもん!スーツの良し悪しくらいわかるよ!」
ぼくはスーツの襟をつかんで言う。
「これはボスに貸してもらったんです」
「違うよ!着こなしでわかる!ジョルノはそのスーツの似合う、偉い大人なんだ!」
そう言うと、キャッキャと笑って見せた。普段はおとなしい優等生なのかも知れないが……本当はじゃじゃ馬なのかもしれない。ぼくの前でようやく素顔が出たのかも。そう思うと、少し愛おしさが増した。
「……まったく元気な子だ……」
さっきまで興奮していたけれど、時間も遅くなって少し眠くなってきたのか、ブローノの質問責めが落ち着いてきた頃、ブローノはオレンジジュースを飲みながら、少しほほを赤らめてもじもじしていた。ずっと出会いたかった唯一の親、精霊の父。きっとぼくも、あの時のギャングがこうしていっしょに遊んでくれたならブローノくらい喜んだに違いない。
「ねぇ、ジョルノ……少しだけオレの話しても、いい?」
少し遠慮がちに、上目遣いにそうきいた。不安げに海の色の眼が潤む。同じ名前を付けても、同じ黒髪でも……性格は全然違うなと思った。こちらのブローノの方が少々、甘え上手のようだ。
……ブチャラティはもう少し不器用というか……甘えることを知らない人間だったな。と思った瞬間、自分がブローノに対して失礼なことをしたと気づき、一瞬目をそらした。
彼と彼が別人なのは当たり前なのに、ぼくは彼と彼を同一人物として見たがっていることに気づいたからだ。
「……ぼく、神父になりたいんだ」
もじもじとストローの入っていた紙袋をいじる手が見える。
「それで……孤児院の手伝いをして……ぼくみたいにパーパやマンマのいない子たちに勉強を教えてあげたいって……」
それでも、ぼくはブローノにブチャラティを重ねて、見てしまった。彼がブチャラティのもう一つの未来であればと思ったのだ。
ナランチャがいつまでもギャングであることを望まず、フーゴに勉強を教えさせ、サンジョルジョ・マジョーレでは引き離そうとしたやさしさ。誰もが有罪だと決めつけていたミスタを救った、正しく真実を見破る目。ブチャラティだけが自分の正当防衛を信じてくれたというその意志の強さ。
窮地にある人間を助けずにはおれないのがブチャラティだった。今思えば、彼自身がいつも窮地にある人間だったので、そういう、救いを求める人々に対する嗅覚が尋常でなかったのかも、と思う。だから、ぼくは思うのだ。彼にはきっと、教師や神父が似合っていたのではないかと。あのブチャラティの広い海のような青い目には、人々の『運命』どころか、それを操る『神』さえも見えていたかもしれないから。
「できれば、あなたみたいにゴッドファーザーになりたい……ネアポリスをもっといい街にできたらなって思うんだ」
そういってブローノはほほえみ、ぼくの瞳をまっすぐに見つめた。
「あなたはオレに、ブローノ・ブチャラティみたいな人になってほしいって、そういう意味を込めてブローノ、と名付けてくれたんだろう?」
ぼくは思わず顔を真っ赤にして、彼の名を呼びそうになった口をふさいだ。
「……ジョルノ?」
涙がこぼれ落ちた。
「ブローノ……」
その笑顔は……一瞬彼が乗りうつったようでもあった。その言葉の先が続かない。何度も言うようだが、ぼくは君のゴッドファーザーじゃない……と。もう、そういう嘘をつくことがバカらしく思えてくるほど……ブローノは、ブチャラティに似ていた。
「も、もういいよ……ジョルノがオレのゴッドファーザーじゃなくても……それでもジョルノは、オレのパーパって事にするから」
ブローノはコルネットを食べ終えると、椅子から降りてこちらへとやってくると、そっと袖を握った。
「ジョルノはやさしいね」
我慢していた涙がこぼれおちた。
「ギャングでもこんなにやさしい人がいるんだ……ジョルノみたいな人がいるから、ネアポリスから怖い人が減っていったんだね」
彼よりも高くて、幼い声なのに……それでもブチャラティが……天国からぼくにそう、感謝を告げてくれたようで……。
そっとブローノの小さな手が、ぼくの頭を撫でた。
「ジョルノみたいな人がきっとギャングスターなんだよ。じゃなきゃ、ネアポリスはこんなにいい街にはならないよ……ありがとう!オレ、もうギャングこわくないや!」
そして、思い切った割にはこわごわと、ぼくの肩を抱いた。
「本当、ジョルノの髪の毛はキラキラしててきれい……さわってもいい?」
ぼくは顔を真っ赤にしながらうなづくと、ブローノはこわごわとぼくの三つ編みをさわった。ふんわりとにおう砂糖のあまいにおい。少し高い体温、小さな手……すべてはブチャラティと正反対でも、その手の感触はどこかなつかしくて……うれしくて……。
「……あっ!星があるよ……」
どうやら、ブローノが抱きついたせいでワイシャツが乱れたらしい。ブローノはうれしそうに襟首から手を入れて、そっと星形の痣に手をふれた。ブローノの早い鼓動が落ち着いていく。
「なんでだろう……オレ、ずっと前にもこうしてたみたいな気がするよ……」
「……えっ!?」
「怒らないでね……なんかね、ジョルノはもっとオレなんかより……バンビーノだった、みたいな気がする……」
一瞬よぎったのは、『運命』という言葉、そして神父が言っていた『天国』という言葉だった。
2
無事にブローノを送り届け、隠れ家に向かおうとした時、なにものかの気配を察知した。五人ほどいる。銃をセットし、握っている。緊張で手がふるえてカチャカチャと銃がしゃべるのが聞こえた。どうやら人を殺したこともない若い連中ばかりのようだ。
「……孤児院に行くのを見られたか……」
待ち伏せしていたということはそういうことなのだろう。逃がすわけにはいかないな。うかつだった。ブローノの顔を見られていやしないかとおそろしくなってきた。
目立たないように護衛は誰も連れてこなかったし、さほど目立った行動をとったつもりはない。誰かぼくの顔を知っているやつらがいて、最初からつけていたということだろう。
ぼくは吸血鬼の力を使って走り出した。わずかの距離を走っただけで、彼らの銃の射程範囲を超える。あわてた暗殺者たちは月光の照らす広場に姿を現した。
その装備は大したことがないみたいだし、ぼくがギャングスターだとは聞いていなかったのかもしれない。
本当にチンピラの寄せ集めだ。青い月光を背に、ぼくは宙を舞っていた。ノコノコと出てきたねずみたちを狩るフクロウのように、音もなく飛んで戻るのだ。
彼らは幻想のような光景に叫び声をながら弾を撃ち放った。
「……ネアポリスのものじゃないな?どこのファミリーかは知らないが……おまえたちを生きて帰すつもりはないよ」
硝煙立ちこめる春の夜。ぼくは石畳に降り立つと、負荷を散らす為にくるりと回りながら降り立った。
「ほんの少しの褒美のためにぼくを相手にするなんて、運が悪かったね」
もう五人とも逃げ腰だった。
ぼくは今宵、何人目を食らうのだろう。命を食らう度、ぼくは数を数えた。それだけの命がぼくの体の中に流れているのだと思うとより冷酷になれた。パッショーネを守るため、これ以上の犠牲を出さないために。
軽く石畳を蹴りあげて、一番油断していた男に飛びかかった。一瞬で消えたように見えたのだろう、銃口をぼくが最初にいた位置に向けたまま、視線を泳がせた。
スーツをなびかせて回転しながら一人目の腹に腕を突き立てた。川が破け、腕に肉がまとわりつく。血が脈打ち、生命の鼓動を感じる。
仲間があっと言う間に串刺しにされてけいれんしている様を見てどよめきが怒ったが、一番短気そうな人間が銃を撃ち放つ。それに気を取り直した全員がぼくに銃口を向けた。
手のひらを広げて胴体が抜けてしまわないように、踊るように回転し、生命エネルギーを体に取り込みながら、ぼくを殺すために放たれた銃弾をその哀れな喰いカスで受け止める。干からびた声を上げて、ぼくの盾は命つきた。腕を引き抜くと、まるで枯れ木のように立ち尽くした死体ができあがっていた。
残る四人を振り返る。敵はゴクリとツバを飲み込みながらこちらを観察していたが、背後にいた人間がぼくに向かって背中に隠し持っていた機関銃を乱射した。きっとぼくを見て簡単に暗殺依頼は終わると思っていたのだろう。あれが本当の彼の得物に違いない。
月光に青白く立ちこめる硝煙。石畳は無惨に飛び散りながら断末魔をあげ、その銃痕を刻んでいく。何発か縫いつけるようにして弾丸を受けたが、血を流しながらも、ぼくが痛そうにする様子もひるむ様子も見せないことに驚いたか、一番おびえた一人に向かって飛び上がって落下し、押しつぶすようにおさえつけ、その背中から胸にかけて貫いた腕を使ってその命を吸い込んだ。
「グギッガアッガ……!!」
顔が干からびていくごとに、蛙のように目玉が飛び出し、みずみずしかったそれは、プチンとはじけて枯れていく。
ゆるやかにやって来た、死の恐怖に満ちた血はあまりに甘美だった。一瞬我を失いそうになるほどに……。罪人の血はぼくに優越を与える。これが野生と言うものだろうか……。負けてしまえばきっとこれを越える快楽が待っているのだろう。
「うひぃいいああああ!!」
混乱して銃弾を石畳に向かって撃ち放ち、跳弾がぼくの首をかする。血がとろりと首をぬらしたが、食らう人間の生命で傷があっと言う間にふさがった。
「……三十四人目です……今の彼で。懺悔はいつも、食事が終わった後にするんだ……君たちだってそうだろう?」
そのまま喰いカスを投げ捨て、銃を握ったまま放心状態になっている敵に向かって走り、心臓に手を突き込んだ。
「だから、行儀が悪いなんて思わないでもらいたい……」
スーツの胸ポケットからハンカチを取り出して手を拭いた。
背後から撃たれた球を受けて、眉をひそめながら振り返る。
「行儀の悪さなら、そちらの方が相当ひどいですがね……もう夜も遅いというのに、そんなにうるさいおもちゃで遊んだら……孤児院の子どもたちが起きてしまいますよ?」
飛び交う銃弾を交わし、滑るように敵の股ぐらに入って足首をつかむ。バランスを崩した人間を振り回し、もう一人とまとめて石畳に引き倒し、腕で貫いた。激しく脈打つ温かい肉の感触。体を満たしていく生命力の充足。
「……三十五、三十六……」
そして体に流れくる生命エネルギーを感じてため息をつく。ぼくを見下ろす月を見上げながら、愉悦にぶるりとふるえた。がらにもなく闘うと血がたぎる。言いしれぬ黒い欲望が湧き出てきた。そしてこうして生命を支配するときが何よりも幸福に思えた。しかし、その幸福感は儚く、あっという間に消えていく。
「……はぁ……は……ぁ……」
生命を与える人間だったぼくは今……こうやって人々の命を奪って生きるむごたらしい生き物になってしまったと気づいたとき、体中を貫く愉悦は全て汚らしいものに感じてぼくは叫んだ。
「ああああああっ!!あ……あ……あああああああっ!!」
ぼくの叫び声に家々の明かりがついた。見られてはまずいとそのまま細い路地へと消えていく。その時、ぼくの腕をつかんだ誰かがいた。
落下するようにして闇に吸い込まれていく。乾いた音ともに、ズブズブと何かに埋もれていく。口の中に入ってきたその味は、ほこりっぽい。体がかゆくなるようなカサカサしたこの感じは……。
「っぺっ!わ、藁?」
藁を積んだ上に落ちたようだ。あわてたようにガサガサ藁をかき分けて、小さな影がこちらにランプの灯りを向けた。
「ジョルノ……大丈夫?」
「……ブローノ?」
ぼくは一瞬、その背後に見た気がした。青い巨人を。
「スティッキィ・フィンガーズ……」
目玉がびくびくとふるえた。うそだ、ぼくはもうスタンドは見えないはずだし、スティッキィー・フィンガーズを使える人間がほかにいるはずがない。
「すごいやジョルノ!どうしてその名前を知っているの?オレの力だよ!念じるだけで彼は動いてくれるんだ!」
「……三十六……人……やっぱり、あの神父が言っていたことは戯言じゃなかったのか……?」
びっくりするほど早く朝が来た。ブローノがぼくを助けるために開いた地下倉庫の持ち主は、どうやらブローノの知り合いのようで、ぼくのためにスープをごちそうしてくれた。
「ジョルノの悲鳴が聞こえたから、はやくジョルノを助けなきゃって思ったんだ……そしたらね、まっすぐに走る道が見えたんだ」
ブローノはぼくの隣でスープの皿で手を暖めるようにしながら丸まっていた。
「でね、彼の名前を思いついたから叫んだら、ビィイイイイってまっすぐにジッパーが走ってね、ぼく、あっと言う間にジョルノのいるところまで着いたんだ」
ぼくは呆然としながら彼のおしゃべりを聞いていた。
頭の中にリフレインするのは神父の声。必要なものは『友』とスタンドを捨てる『勇気』、転生した自分を目覚めさせる『十四の言葉』、そして……『三十六の罪人の魂』……。それが、さらなる命の先、目指す『天国』への条件……。
「か、体はなんともないんですか?」
ブローノはうれしそうにほほえみながら首を横に振る。
「だいじょうぶ!それよりもオレ、ジョルノに力が見えて良かったって思う……どうしてだろう?」
スープを飲み終えると、ブローノは飛び跳ねてぼくのそばを立ち、壁に小さなジッパーをつけて覗いていた。
「……あれが、ジョルノの力?」
そう言ってブローノが穴の先を指さすから、ぼくもスープをあわてて飲み干して床に皿を置き、ブローノの作った穴を覗いた。
五人の死体があるはずの場所は、緑の小さな森に変わっていた。
ぼくはうち震えた。そんなわけはない……そんなわけは……もういつの間にか彼の姿を十一年も見ていない……。
おそるおそる、後ろを振り返る。
そこにいたのはまるで黄金でできたかのような少年兵が立っている。
「……ゴールド・エクスペリエンス……」
3
執務室の机の上に、不自然に一匹の亀が住んでいる。椅子に座ると、その亀の甲羅に埋め込まれた鍵を飾る、赤い宝玉に手をふれた。吸い込まれていくぼくの手を、無邪気なブローノがつかんだ。
この危険な状況の中でブローノを一人にするわけにもいかないし、そもそもあの孤児院が危ない。一刻も早く何らかの対策を練らなければ……そう思って帰ってきたのは隠れ家のホテルだった。
ブローノのスティッキィ・フィンガーズの勢いに乗り、ゴールド・エクスペリエンスでぼくらの姿を見つけた人間の目をくらましながらここまでやってきた。
こういう事態で一番頼りになるのは彼しかいない。ジャン・ピエール・ポルナレフ……。
亀の中とは思えない広さの部屋に、骨董物の家具が備え付けてある不思議な空間。ブローノは目を輝かせて部屋の中を見渡した。
「直接会うのは久しぶりだなジョルノ。ずいぶんと一人を満喫していたみたいじゃないか。隠し子までいたなんてビックリだな」
そう言って笑うポルナレフさんをにらみつける。
「ち、違います!こんな大きな子どもがいるわけないでしょう!」
しかし、ブローノを見るポルナレフはおだやかな表情をしていた。
「オレは今まで不思議な経験を山としてきた。死んだと思った人間が実は生きていた……とかな。だからちょっとやそっとじゃ驚かないが……」
ブローノはポルナレフさんに気づくと、ピッとたたずまいをただして頭を下げた。
「ブッディストが輪廻転生とかいうやつだろうか?これは……驚いた……」
「ぼくも……です……」
どういう顔をしていいのかわからないが、やはりブローノは、ブチャラティの生まれ変わり、ということらしい。
ぼくはプッチ神父から聞いた『天国』への条件を話し、ブローノとの出会いも話した。ブローノは今テレビのアニメ番組に夢中になっていた。どうしてカメの体の中なのにテレビがつくのか、そちらに興味を引かれているようにも見える。
「ところでジョルノ、スタンド能力がいつ戻ったんだ?」
車椅子に乗った、重力に逆らう銀髪の青年は、口を開く。
全ての戦いが終わり、体から矢が抜け落ちて数日後、たった一週間と少しだったものの、すさまじい連戦を乗り越えた後、一気にガタが来たみたいにぼくの体は変化をしていった。
スピード・ワゴン財団の使者を名乗る男が現れ、ぼくの体が吸血鬼へと変化していることを伝えられた。原因は、矢によるスタンドへの過度の疲労。それをまるで見計らっていたように、ぼくの体の中に眠っていた吸血鬼、父、ディオ・ブランドーの能力が蘇っていったのだった。
「なるほど、息子であるおまえも父と同じ『運命』を歩んでいると神父は言ったのだな……」
ぼくはうなずいた。
「でもぼくは確かに神父から父の遺骨を見せられた。ポルナレフさんだってぼくの父が死んだところを確かに見ている……もうぼくには血縁はいないはずだし、ともに『運命』を歩む人間だっていないはずだ」
仲間であるミスタやトリッシュはあくまで仲間であって血縁ではない。本当の時はそれぞれの血に流れる運命をおのおので受け止めなければならない。今、こうしてぼくが『運命』を目の前にしているように。
「……それなのだが、おまえに神父の話を聞かされてから、スピード・ワゴン財団はこっそり同行をうかがっていたのだが、今、君と同じ血を引く友人の娘が、今まさに『運命』と戦っていると言うんだ」
ポルナレフさんは亀の中にある時計を指さした。
「……気づいていたろう?時間が加速していることに」
「……うすうすは……」
気のせいだと思っていたが、気のせいではなかった。確かに時間は加速している、それは消えた三秒のようにあいまいではなく、はっきりと物理的に加速を感じていた。
「おまえはまだ、石の矢を持っていたな?」
「……はい……」
胸ポケットから大事にハンカチで包んだ石の矢を取り出す。その危険な能力を心配してでもあるが、肌身話さず持ち歩いている。アバッキオ、ナランチャ、そしてブチャラティ……三人の意志をぼくに受け渡した形あるもの。意志の矢。彼らの意志はいつも共にぼくの胸にある。
「二つの石の矢は、二つの平行した運命を真っすぐに指し示しているのかもな。今、おまえの血縁である娘が戦う男の持った矢と、おまえの矢」
何が起こるというのだろう。
「彼はぼくがスタンドを矢で貫いてその先の力を見たことを知っていていたから……『天国』のことを教えたのか?」
ぼくの『運命』は、その『勇気』を持って背後の光を打ち壊してスタンドを捨てたブチャラティという『友』に宿り、ぼくたちの思い出をつなぐ『十四の言葉』の代わりとなる品に触れ、そして『三十六人の罪人の魂』を吸ったぼくの元へと再び帰ってきた。
「ぼく、自分の父のことを知らないとと思ったんです。ブチャラティが叱ってくれた……ぼくは『運命』を見ることをおそれていると……」
きっと矢は、ぼくが動き出したことを感じたのだ。
「『運命』なんて見なくとも生きていけると思っていた。ぼくは闇の先を予想し、『覚悟』で道を切り開いてきた……」
でも、ぼくは怖くて星空を見上げることができなかった。それを認めることは『覚悟』もまた『運命』のしわざとなる。そこに人の意志はない。ブチャラティを魅了し、その魂を連れ去ってしまった不可思議な力が怖かった。
「彼はぼくに、あまり地上の闇ばかりを見つめるなと言った。そして、ぼくに空を、星を見るようにと教えてくれた」
空を見上げると、運命という名の宇宙がぼくを押しつぶしてしまうような錯覚にとらわれた。でも、ぼくにはブチャラティがいてくれた。不安を見せたぼくを包み込んで励ましてくれる、大きなやさしさの人が。
「地上を見ることも大事だが、空を見ることも大事……良いことを伝えてくれる友人がいてよかったな」
ポルナレフさんはうなづいてくれた。
「……叱らないんですか?こんなにもメチャクチャになったのは、ぼくの責任かもしれないのに」
ポルナレフさんは笑う。
「奇妙な出来事にはずいぶん慣れているさ。おまえを叱ったところでこの状況は止まるのか?はるかアメリカで動いているこの『運命』を?」
「……アメリカ!?」
その力がこのイタリアにも及んでいる?では、ぼくの血縁者が今現在対峙している敵、プッチの力はどれほどのものだと言うのだろう?いや、これが『運命』なのか?
「それどころか、地球全体に及んでいるよ……ディアボロの比じゃない……」
ポルナレフさんは厳しい表情を浮かべたが、やがて苦笑しはじめた。
「オレは、ジョルノ、おまえのことで不安に思ったことは一度もない。その友人が残した願いはあまりにやさしく誠実だった。おまえはその願いを叶えるために、ずっと戦ってきた。オレはそれを見守ってきた……」
コホンっとポルナレフさんは咳をする。
「そう、幽霊だしな。もう私には肉体すらない……だから、もう、できることはその地球全体を取り囲んでいる『運命』って力を見守ることだけさ」
そう言って、ちらりとブローノの方を見る。今はテレビに飽きたのか、熱心に聖書を読んでいた。そう言えば、神父になりたいと言っていたっけ……。彼もまた、運命をまっすぐに見つめる『覚悟』を持つものなのかもしれない。
「そして、おまえはその渦中にある」
首を横に振り、両腕を広げる。
「その、肩の星形の痣はな、ジョースターという一族特有の遺伝だとスピード・ワゴン財団から聞いた。おまえには二つの血筋が流れている。黄金の魂を持つジョースター家、そして、漆黒の意志を持つ吸血鬼、ディオ・ブランドーの血筋」
ぼくは定期入れを取り出して写真を見た。こちらに背を向け、星形の痣を見せる男の写真を。
「もしもおまえが、ギャングスターになるという夢だけで行動していたらどうなっていたかわからん。それこそ本当にディオの息子として横暴な振る舞いに変わっていった可能性もある」
ぼくは違和感を覚えてポルナレフさんに質問をした。
「……なぜ、ぼくをブランドー一家として扱わないのですか?吸血鬼にまで変わったぼくは、明らかにブランドーの血筋を強く受け継いでいるのに!」
ポルナレフさんは食ってかかるぼくに対してもおだやかにほほえむ。
「オレは今まで、ジョルノ、おまえを見てきた。そしておまえを変えたブチャラティ、オレは二人の戦友を信じることにしたんだ」
ぼくは定期入れをズボンのポケットにしまうと、そっと矢といっしょに入れていた小さな髪飾りを取り出して口づける。
「……ありがとう、ブチャラティ……あなたがぼくの『運命』を変えてくれたんですね……ありがとう、ポルナレフさん……」
うつむいて小さくつぶやくと、ポルナレフさんの口元が少し弧を描いたのが見えた。
「そうだ。おまえなら悪魔の血筋も乗り越えられるさ。トリッシュのように」
ぼくの体の中ではきっと、二つの血筋が争い続けているのだ。黄金の魂と漆黒の意志が。ブチャラティという友を失い、ぼくはまた闇ばかり見ていた。だけどまた、バンビーノ・ブローノのおかげで思い出すことができた。……星を見ることを……。
4
街ではあちこちで悲鳴が、困惑の声が上がっている。丹誠込めてそだてたオレンジがあっという間に腐り落ちて落胆の涙を落とす婦人がいたし、落下したペンで足を砕かれた営業マンがいた。
あっという間に何もかもが風化していく。ぼくはブローノに手を引かれて太陽の下を走った。ぼくの肌が焼けていく。まだ完全に吸血鬼の体が人間になれたわけではない。時間だけが過ぎていく。ぼくの体の変化は追いつかない。
これ以上の変化が起こる前にとブローノを孤児院へと戻そうと夜を見計らって外出したのだが、時間の加速が思った以上に進み、太陽の光にグズグズと焼けていく体を引きずりながら走っていた。
「……ごめんなさい……ぼく、こんなつもりじゃ……」
ようやく駆け込んだのは孤児院の教会だった。後少し走れば孤児院にたどり着くが、ブローノは扉を閉めるとそれを背にして首を横にふった。
「あなたが大変なことになること知らなくて……」
そう言って火傷にただれたぼくをギュっと強く抱きしめてくれた。
「いや、いいよ……ブローノ、君がスタンドを使ってぼくを助けてくれなければここまでもたどり着けなかった」
教会に飾ってあった時計の針は勢いに被いのガラスを打ち抜いて抜け落ち、窓はひっきりなしに朝と夜を繰り返した。
たった二人、教会の教壇の前にに座り込み、変化する世界にどうすることもできぬまま、懺悔するでもなくぼんやりと十字架をながめていた。ステンドグラスの光が落ちて、世界が虹色に輝いている。
「ねぇ、ジョルノ、ぼくの血を吸って……」
ブローノはそう言ってワイシャツのボタンをはずして首筋を露わにした。
「ブローノ、ぼくが吸う血は罪人の者だけ、吸血鬼になったときから、それをずっと決めているんだ」
正しき者は死んではいけないし、未来ある子どもならば、もっといけない。
もうじきぼくは死ぬのだろう。少年の白い肌や服に、ぼくの乾いた血がこびりついていた。払いたくても、触れた先から彼が汚れてしまうと思うと、とても触れることはできなかった。
「君はとても清らかだ……罪にまみれたぼくの体には、その血は毒なんだよ……何度も言ったじゃないか……ぼくは君とは何の家計もない人間だって……だから、悲しんじゃだめだ……」
小さな体は背中を丸めてもっと小さくなり、さみしげにすすり泣いた。
「ぼくには、あなた以外、家族が居ないんだ……そんなこと……言わないで……」
そうだ、ぼくもきっと、あの時ぼくを救ってくれたギャングに『おまえなんて知らない』なんて目の前で言われたら……どんな思いをするだろう。
ああ、体が吹き出す体液にバリバリに固まっている。もしかすると、ぼくが思っているより長い間、彼を見守ってあげることができるかもしれない……。神様……ありがとうございます。過酷な運命ばかりを授けたあなたでも、世界の終わりの今日ばかりは、やさしいのだろうか…。
ブローノは手を組んで十字架をじっと見ていた。
「……ブローノ、この十一年間、そうやってずっと祈り続けてきたんですか?」
この教会で、ずっと……たった一人、精霊の契りを結んだまま、一度も会いに来なかった父親を待って……。
ブローノはほほえんでうなずいた。
「ぼくの隣にも、そんな人間がいました。父とも母とも、兄弟ともつかない……でも家族のようで、何かで結ばれている間柄のような……、彼はぼくなんかと違って……ずっと敬虔だった……」
一度だって彼が祈っているところを見たことがない。いつも彼はまっすぐにぼくと一緒に闇をにらんでいた。ブローノ・ブチャラティ。ぼくに生き方を教えてくれた人。『運命』に殉じた騎士。
「あなたはその人になんだか、似ているんだ……」
彼の命日に拾われ、よく似た黒髪で……あの時はわからなかったけれど、今こうして深い海のような瞳でみつめてくれる……。思わず、強く抱きしめてしまった。ブローノは少しくすぐったそうに笑った。
その瞬間、胸ポケットに違和感を覚えた。あの矢が、動き出している。
ブローノをそっと引き離して、ハンカチから矢尻をとりだした。アバッキオ、ナランチャ、ブチャラティ……三人がぼくに受け渡してくれた意志。
「これは、彼らにもらった大切な意志。残酷だけど……とても手放すことができない『運命』……」
こんなぼくを言うのかもしれない。ブチャラティが言っていたなぞめいた言葉、『運命の奴隷』。
矢はぼくの手の中でくるくると回り、ブローノに向かって先をぴたりと止めた。
ブローノはまるでその矢から目が離せなくなったように息をのみ、眠り姫のようにおそるおそる、禁じられた糸車にふれようとするように矢に触れようとした。
「ブローノ……?」
彼の目はどこともしれぬ場所をながめながら矢に触れようとした。
その瞬間、ついに劣化が進んだ十字架が倒れ、ブローノの肩から心臓へと肉をえぐりとった。体が弾けたようにしてぼくの体の上に倒れ込んだ。
ぼくの胸に抱かれたブローノは大きく目を開いてけいれんしていた。
「……あ、あ……」
体から生命が枯れていくのがしっかりとわかった。サンジョルジョ・マッジョーレの光景が思い浮かぶ。倒れたブチャラティの体、見開かれた瞳にはもう光は宿らず、その上に汚らわしいハエが止まる。
肩から胸にかけて大きく裂けた傷は、どう見ても致命傷……。
だけどブチャラティは……ぼくを守ろうとして起きあがってくれた……。
「ゴールド・エクスペリエンス!」
もう一度奇跡を起こしたくて叫ぶ。
二度も神の前でブチャラティを失いたくない。
これが運命だなんて思いたくない。
「ゴールド・エクスペリエンス!!」
胸が苦しくなり、呼吸がままならない。
ブチャラティを失おうとしているぼくの意志が錯乱しているせいか、ぼくのスタンドは姿を現さなかった。ぼくの脈打つ心臓の音が聞こえる。目の前でブローノの死体は放っておけばあっと言う間に腐り落ち、土に変わってしまうだろう。
ぼくは、まだみずみずしい少年の首筋についにかじりついた。
弱々しい生命力がぼくの体に……流れ込む。そのまま、少年の体に意識を集中していく。ゴールド・エクスペリエンスが、ぼくとブローノの体ごと抱きしめた。少年の体に生命エネルギーが流れ込み、その乾いた血は花になり、蝶になり、蔦をはわし、ぼくたちを包んでいく。
もうすぐこの白雪姫は目を覚ますだろう。
ところが、あの残酷な矢はぼくに向かって再び先を向けていた。
しかし、今のぼくはもう『運命』を怖いとも残酷だとも思っていなかった。『運命』という力を知り、見つめることは確かに必要なこと。それは闇の中にある道を創っている。闇を切り裂き歩くのは、『運命』の創った道。
ぼくの命を奪おうというなら奪うがいい。だけどぼくはそれでも真っ正面から『運命』と戦うだろう。
ブローノの体を横たえ、ぼくをにらみつける石の矢をとりあげて、星形の痣に自らの意志で突き立てた。
終章 円舞曲
聞こえた気がする。とても軽やかな三拍子が。
一頭の馬の駆け足。加速していく三拍子。ワルツにはちょうどいいが、少し早すぎる。ぼくの手は、踊ってくれる相手を求めて宙をさまよう。
このイタリアだけじゃない。『運命』という力は地球を囲い込んで、どこでも試練を起こしている。その試練の先をどこかで今、一頭の馬が駆けている。
どこかで今、一頭の馬が駆けている。
雨が肌をたたきつける感触で目が覚めた。いつの間にやら教会は朽ち果てて木製の屋根は腐り落ちていた。
空を見上げて唖然とする。空にまっすぐ一本の光輝く線が、巨大な虹のようにかかっていた。それがものすごい勢いで軌道を描く太陽だと気づくのにずいぶんと時間がかかった。
あわてて少年の血でできた草原の中を起きあがる。草や蔦に埋もれた少年の体をなんとか掘り起こそうとしたが、フッと動きを止めた。
「……ブチャラ……ティ……」
絡みつく蔦や、肌をなでる草花に囲まれて、白雪姫が息をしていた。それは成長したブローノだった。
彼を生かそうと流した生命エネルギーが過剰に流れ込み、成長させたというのだろうか……。そして、ぼくの体は……。
「……こんなに太陽の光に照らされているのに……朽ちもしない……」
うれしくなった。ぼくは叫びそうになった。ぼくとブチャラティは生きている。
そういえば矢はどうなったんだ?と肩に触れると、そこにちょうど矢尻をかたどったようなくぼみを見つけて、ドッと冷や汗をかいた。
「ヨウコソ、天国へ」
無機質な声が響きわたり、振り返るとそこにいたのは……四月六日、雨上がりのあの日見た……ゴールド・エクスペリエンス・レクイエムだった。
「天……国……」
ぼくの腕の中にいたブローノはぼくの愛した記憶の中のブチャラティそのままだった。
「あの神父が言っていた『天国』がここだって?」
「ソウダ。アナタハ奇しくモ、知らぬ間に父ト同じ運命ヲ辿ったノダ」
ゴールド・エクスペリエンス・レクイエムは感情のこもらぬその瞳で、じっとこちらを見つめていた。
「アナタの父ガ目覚めた瞬間、同じ血族であるアナタと父の血ハ共鳴ヲ始めた」
ぼくが矢を刺したことにより、ゴールド・エクスペリエンスに届いたのだろう。ぼくはまだ『運命』のレール上を辿っていた。
「シカシ、アナタの父はもう一人イル。己だけノ為ニ『運命』を辿らなかったアナタハ別の道ヲ歩むコトにナッタ」
ぼくが、ブチャラティと出会ったから、お互いの心の淀みを吹き飛ばしあい、どちらか『運命』の壁の大きさにひるみそうになっても、横を振り返れば彼がいて、視線を交わせば無限の勇気が体を駆け巡った。
「ソウ。父は嫉妬にカラレテ星を見ナカッタ。ダケド、アナタハ……星を見るコトヲ教えラレタ。愛する人ニ」
ぼくはブチャラティの願いがあったから生きた。もし、ブチャラティが生き残ってぼくが死ぬことがあってもきっと、ブチャラティはぼくの夢のために生きてくれるだろう。
「アナタは彼と会うコトデ貪欲に、サラに生命のソノ先ヲ望ンダ……」
そういう関係だったからこそ、ぼくはこの世界の理を覆してでもブチャラティに生きてほしいと思ったし、これで『運命』からブチャラティを救えたとも思った。しかし『運命』はそのぼくが与えた『生』という結果を使ってさらにブチャラティに試練を与えた。
「アナタが最も畏れてイルノは『終わり』ダ」
なぜか心臓がぎゅっと捕まれたように苦しくなった。
「アナタが最も畏れてイルノは『死』ダ。ダカラぼくハ生マレタ」
母が残したごくわずかの食べ物を食べ、暗闇の中の姿のない何かにおびえた。父からの虐待で生命の危機をさまよい、慣れないイタリアでは母からの食事すら望めない状況にもあった。
だからぼくは漁るように知恵をつけた。たった一人でも生きていけるように……。そんなときに出会ったのは、あのギャングだった。ぼくの人生は好転していく。父と母に願い出て中学の入寮にこぎ着けたのは本当にありがたかった……きっと、あのギャングの力もあったのだろう。
「アナタは、『死』を認めなかったカラ生き延びるコトガ出来た。ダカラ、死を認めないアナタは他ノ生物にもにも『生命』ヲ与えテ抵抗シタ」
本当は知っていた。サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会でブチャラティが死んでいたことを……。でも、心がそれを否定し続けていた。必ず、どうにかしてブチャラティを救えるものだと信じていた。
なんとか草花からその裸体を引き出すと、とりあえず体が冷えないようにスーツの上着をかぶせ、そしてその体温を確かめるために抱きしめた。ぼくの腕の中にはまた、あの時と同じブチャラティが眠っている。
まだ生きてはいるが、その左肩から胸にかけての傷口が生々しく盛り上がっているのを見ると、心が痛んだ。よほど痛むだろうに、彼は悲鳴も上げない。
「今抱いているソレガ『死』ダ」
おそれずに『運命』に殉じることを選ぶブチャラティ。彼そのものがぼくと正反対の死の象徴なのかもしれない。『運命』に向かって歩み、『運命』のつきた時点でその命を終えることを最大の使命として生きた彼。ぼくには彼のそんなところが理解できなかった。
どうしてあがかないのだろう?どうして、こんなにも素直にいられるんだろう?
そして、そんな無私なところを……魅力的だと思ったのだ。
「ココは、アナタの望んだ『天国』。『終わり』のないノガ『終わり』。ソレガ、ごーるど・えくすぺりえんす・れくいえむ」
空中に浮き上がり、燦然と輝く自分のスタンドを見上げる。
「……『終わり』のないのが……『終わり』……」
ぼくは呆然としながらステンドグラスの虹色に照らされて宙に浮かぶ、もう一人の自分と見つめあった。これが、生命のその先の具現化。
その時、ブチャラティが目を覚ました。十一才だったころの衣服は、そのふくれあがったたくましい体に引きちぎれ、用をなさなくなっていた。ぼくの上着でなんとか、大事なところは隠した。
ようやく目覚めた彼は、じっと深い海の色をした瞳でぼくを見ると、そっとなぐさめるように、ほほに手を触れた。
「どうしたジョルノ……なぜおびえている?」
運命は死をもたらす。使命は果たされる時がやって来る。使命の終わりが訪れれば、その運命の使者との別れがやってくる。
「……ブチャラティ……」
強く抱きしめる。ここはぼくの『天国』すべてをループさせて過程を繰り返すことで終わりをなくした天国。
今、地球上に訪れた『天国』は、終わりを早める力を持っている。やがて生命体である地球そのものがその『運命』を終えるだろう。
「今、ワタシが『終わり』をクイ止めてイル。ワタシの能力を切れば、生命体、地球が『終わり』を迎える」
ぼくの瞳からこぼれ落ちた涙が、ブチャラティのほほにかかった。
「……なぜ……泣いている?」
少し八つ当たりするようにぼくは言う。
「あなたのせいだ……あなたのせいで……こんなにも残酷な選択を迫られているんだ……」
それでも彼は、困ったようにほほえんで、そうか、とつぶやき、ぼくを責めようとはしない。その大きな体で……いや、今は少し、ぼくよりも小さい体で抱きしめようとしてくれる。
「あなたがあんまりにも純粋に、『運命』を見るから悪いんです……」
もっとぼくといっしょに生きることを選んでくれる人ならよかった。
「……嫉妬している?」
そうです。絶対に敵わない、姿さえないやつに嫉妬している。
「あなたを奪うのはいつも……『運命』だ」
当たり前だ。あなたと運命は引き離せない。あなたの澄んだ海のような瞳はいつも空を見て、運命を見据える。己の終わりを目指して歩く。
「でも……ぼく……精一杯あがきました……。でも……運命はそれでもぼくをがんじがらめにしていた……最初から逃げきることなんてできなかったのに……」
結局二度、あなたの命のろうそくは灯りを消した。
「オレはおまえが誇らしいと思う」
あなたはそうやってすぐにぼくを甘やかそうとする。
「なんで……ですか!!ぼくは結局……一番来るのを畏れていた終わりを目前にしている!!止めている能力がぼくの力だとしても、ずっとこのままでいられるわけがない!!」
ブチャラティは八つ当たりするぼくにも動じず、ただじっと見つめている。どんな激しい感情でさえも全て、その瞳の海に吸収してしまおうとするように。
「ずっとずっと……運命の手のひらで踊らされていただけだった……」
それはまるで、終わり無く単調な音を繰り返す三拍子のよう。
「……滑稽だ……ぼくは一人でワルツを踊っていたのか……」
天を見上げる。朽ち果てた屋根の向こうに見えるのは、まるで虹のように空にかかる太陽の軌道の輝き。天体でさえリズムを崩さない。地球の運命から逃れたとしても、きっとまた違う星の運命が捕らえにやってくる。
闇の向こうにある道は、運命が最初から開いていた道。
乾いた笑いを漏らす。甘えてしまおうか……自分のスタンドに。大嫌いな『終わり』をもたらさないために『終わり』がないのが『終わり』だという、この能力に。
その時、すがるように動いた体が、ぼくをしっかりと抱きしめた。あたたかい体温がじんわりと伝わってくる。そしてやさしくトントンと規則正しいリズムでぼくの背中をたたく。
「オレがいるだろう、ジョルノ?」
「あなたとぼくは見ているものが違う……あなたは終わりを愛している!!」
振り払おうとするが、そんなことをしていいのかと一瞬ためらった。結局のところ、どうあがいてもぼくは彼が好きなのだ。
赤面していくぼくを見て、ブチャラティは、ほほえんでいる。
「ひとりぼっちでワルツを踊る君に、お誘いをさせていただいてもいいかな?」
「……何を……」
さっきの独り言みたいな八つ当たりの言葉を蒸し返されて恥ずかしかった。
「ジョルノ、おまえ一人では危なっかしすぎるんだ……」
運命にとらわれる囚人は二つのタイプがあるのかもしれない。
泥という名の闇深い大地しか見えない囚人はきっと、空から降ってくる物に気づかない。星という名のきらびやかな空しか見ない囚人はいつかは石や大地の隙間に足をとられて転ぶだろう。
だけどもし、その全然違う方向を見る囚人同士が手を取り合って助け合えば……ちょうどいいかもしれないじゃないか。
「……男同士でワルツなんて、楽しくないんじゃないですか?」
ブチャラティはふざけてぼくの上着を腰に巻いて、スカートのようにめくりあげる。
「そこそこ色気は自信があるぞ?」
「……どこからそんな自信がでてくるのやら……」
「……なんだよ……誰が最初にオレを抱いたんだ?」
ブチャラティの腕が、ぼくの首に回る。
「……耳まで真っ赤だ……説得力がないぞ……」
愛おしい。その雪のように白い肌もその血が滴るように赤く濡れたくちびるも、その黒壇のように黒い髪も……。わき腹に手を滑らせ、その体の確かさを感じる。十一年間ずっと、そばにほしかったその体を。
「……本当、変わらないな……少しの誘惑で目がくらむ……」
「相手が、あなただからですよ……」
おもしろそうにクスクス笑うその顔は、ぼくの愛撫に興奮してか、しっとりと汗をかきだした。
だけど、ぼくはレクイエムの視線に気づいて愛撫を中断する。
「君を解除すれば、すぐに世界が新しく生まれ変わるのか」
ぼくの質問にレクイエムはうなづく。
「『終わり』は、すぐにヤッテ来る」
加速した時間はあっと言う間に地球を殺す。その先、この能力者がなにをしようとしているかは知らないが……それだけは確実だ。
「ぼくにはもう迷いはない。最後まで運命の手のひらで踊ろう。でもこれは運命の意志じゃない。ぼくの意志で選んだことだ」
そう言うと感情のないレクイエムの瞳がきらりと輝いた気がした。
「暗闇を裂き、ソノ道の向コウへ……了解シタ。我ガ主よ」
もう終わりは怖くない。ずっとそばに居てくれようとするブチャラティがいるから。
「いいのか?世界が滅んだら、オレもおまえも死ぬんだぞ?」
「死なないかもしれない。先を見なければ誰にも確かなことはいえない」
ブチャラティのほほにかかった黒髪をそっと耳にかけると、彼は小さくほほえんでみせた。
「何もかもを肯定し、なおかつ先へ進もうというのか」
そう、貪欲に。時間の先へ、未来へ。なにがあるかわからない未来へ。
「そこには希望がある。運命はきっとぼくに幸運を与える」
これは、自信じゃない。確信だった。
死をも逃れるチャンスを与えてくれた『運命』は、ぼくのことを相当気に入ってくれているはずだ。ただ少しぼくを振り回し、揺さぶりをかけ、寵愛にふさわしい人物か試そうというのだろうけど、ぼくには運命をその瞳に映すブチャラティがいる。その姿をはっきり捕らえれば怖ろしくもない。これからはもう惑わされない。
「それもこれも、あなたが、アバッキオとナランチャが意志の矢を残してくれたおかげです」
矢は、今はぼくの体の中へ。運命の意志はぼくの方向を向いている。
おかげでぼくは観測者になれたということだろうか。平行する世界の一部を形成できたということか。ほんの少しでも、こんな経験が出来たことを誇りに思う。
「ただ、まっすぐにあなたを愛します……あなたが運命を愛するみたいに……」
ワイシャツのボタンをはずしていくと、うっとりとしたブチャラティの手がぼくの胸板を撫でた。
「……力強い鼓動だ……」
「……若いからです……」
例え二十六になって、あなたよりも六つ年をとっても……
ほほえみながらブチャラティはぼくの腰に手を回した。あたたかい体温が体を包み込む。ほそめられた目蓋からのぞく深海のような瞳をまっすぐに見つめ、ぼくを求めてうっすらと開くその口の中に舌を差し込んでいく。
うっとりと目を細め、ブチャラティの舌がぼくを迎えにやってくる。
ずいぶんと積極的なのは、彼もまたずっとぼくを求めてくれていたからなのだろうか?
十一年ぶりの抱擁はお互いを高ぶらせたのか、珍しく感情的にさせた。愛おしい思いはその人の体温に溶けだして、その滴は涙になってほほを濡らした。
こすれあうだけで、屹立した敏感な部分がピクンと動く。舌の根本に当たると、やさしく撫でるようにからませあう。
恥ずかしそうにブチャラティの体は震えている。ぼくはそのほほを撫で、小さく呼吸しながら久しぶりに感じたブチャラティの体温を体中で確かめる。
「っは……あ……たくましくなったな……ジョルノ……」
くちびるが離れると、お互いの距離を無くすようにほほをすりつけあう。ブチャラティの手はそっと撫でるように首筋を通り、胸板を撫でる。
「……あ、あなたに……ほめられるなら……この十一年間の孤独も……無意味じゃなかった……」
ぼくが笑うと、ブチャラティもぼくの肩に顔を埋めて笑う。
「ああ、無意味じゃなかったな……本当にいい男になったよ……」
ただ運命にもてあそばれた十一年間。あなたといた一週間と少しの時間、そこにあった輝きはなかった。だけど、ぼくは自分の『運命』と戦う強さを身につけた。
血と麻薬と怨執、まだ若く手段の無かったぼくは、抗争を力で押さえ込むしかなかった……道を間違えたかと不安に思ったこともあったが……それでもぼくいは『覚悟』があった。
ただ、あなたの願った麻薬のない、街の人々が屈託なく笑うネアポリスが見たくて……。そうしてがんばっていたから……あなたに頼られる男になれただろうか……?
ブチャラティの腰に手を回し、腰を撫でると、恥ずかしそうに脚を開いた。
「おや、ブチャラティ、おねだりを覚えたんですか?」
ぼくが意地悪く言うと、顔が見る見る真っ赤になった。
「……じ、時間がないからな……」
「ええ、きっとこのまま時は加速し続ける……そうなったらまた……あなたと離ればなれになるかもしれない……」
もうそこに悲嘆はないけれど。
「でもまたきっと『運命』がほんの少しでも、ぼくとあなたを引き合わせてくれる……」
お尻の肉をひらくようにしてなぞり、すぼみに指を入れると、あま勃ちしていた陰茎がグッと持ち上がった。
「……っ……あっ……」
「……あんまり、指をしめないで……折れたら……どうするんです?」
したたり落ちる透明の滴を指に絡ませてゆっくりとほぐしていく。
その間、不安そうにブチャラティはぼくの首に腕を回して力をこめていた。
「……久しぶりだと、少し怖い……」
ブチャラティの内腿に力がこもったのがわかった。恥ずかしそうに、やさしくな……?とささやいてくる。
「……怖いなら、抵抗してもいいんですよ?」
そっといじわるをささやくと、ブチャラティは困ったように眉をひそめた。
「……ふふっ、オレはマグロだからね」
「……まだそれ、根に持っていたんだ……」
緊張で力のこもった入り口に先端を入れる。
「……うっ……ふっ……」
力を緩めようとする動きと緊張で穴がまるで吸いつくようだった。
「戦っているときのあなたはとても凛々しいのに……まるで子どもじゃないですか……」
ブチャラティは少しだけムッとした顔をした。ぼくは笑いながらブチャラティの耳に顔を近づけた。
「さぁ、覚悟を決めてくださいよ……力、抜いて……」
戦闘の時の痛みに耐えられても、こういう事に対すると、とたんに痛がりな彼が好きだ。
ツンっと勃った乳首を指先でいじると、ハァっと熱いため息が漏れる。指で摘み、こねながら片方の手でわき腹を撫でる。
見つめあい、彼を安心させながらゆっくりとゆるんできた穴にゆっくりと奥深く挿入していく。
次第に心地よくなってきたのか、腰が動き出した。ねだる動きにブチャラティの陰茎がワイシャツにあたり、先端からとろとろこぼれる精液で汚れていく。腰と腰が当たるたびにクチュクチュと音が響いた。
「……んっあ……っ……んっ……」
ブチャラティは声を上げて、はずかしそうに顔を隠した。
「っ……ブチャラティ……すごく……あなたの体……吸いついてくる……」
だんだんとこらえきれなくなる。ぼくだけじゃない、ブチャラティもぼくを求めてやまないんだ……だんだんと動きに遠慮がなくなってくる。
次第に自分の快楽に没頭し出すと、ブチャラティのほほえみが見えた気がした。あの時のように……ぼくを甘やかしてくれる腕の中で果てる。
もうすっかり安心したようで締め付けも緩やかだ。腰を振りながら見つめあい、軽く口づけあい、お互いの体をつなぐ部分が与える快楽に浸った。
この行為に執着がある訳じゃない。ただ思い出がほしいだけだ。脳に刻みつけられる、この……瞬間が……。
頭の中が真っ白になる。ブチャラティの中にぼくは劣情をぶちまけ、招くタナトスに不安でいっぱいになる。でも、その確かな彼の腕は、自分の体に倒れ込むぼくをギュっと力強く抱きしめてくれるのだ……いつだって。
ブチャラティの胸に顔をうずめて涙を流す。
「……よくがんばったな……」
「がんばりましたよ……あなたのために……」
萎えたものが自然に抜けるまで……。
「もっと一緒に……ネアポリスを歩きたかった……」
「大丈夫だ。ずっと見ていたよ。真っ白なブローノとして……誰もがうらやむ街、ネアポリスを……」
◇ ◆ ◇
「このスーツ、高かったんですよ?……すっかりあなたのにおいが染み着いてしまった……」
ブチャラティの体に上着を掛けて、じっと見つめあう。
「……どうせこの能力を解除したら、あっと言う間に塵に変わるさ……」
笑うブチャラティは、心の底から運命にもてあそばれるのを楽しもうとしているようだった。ぼくはまだ少しだけ、能力を解除することをおそれているのに、もう彼の腹は決まっているのだ。
「そうだブチャラティ、これをあなたに返さなくっちゃならない」
上着のポケットから取り出したのは、いつも彼がつけていた小さな髪飾り一つ。本当は二つで一つなのだけれど、もう一つは今、彼の故郷で海を、子どもたちを見守る大樹に育っている。
「ふふっ、なんだかずいぶんと懐かしく感じるよ……」
頬にかかる髪を右手ですくい上げて、そっと右耳にかかるように髪飾りでとめた。その仕草はなんだか、少し色っぽい。
「……ずいぶんと懐かしくて当たり前です……ぼくたちがこうして出会うのに、十一年かかってしまった」
あらわれた右頬に軽く口づけると、ブチャラティはうれしそうに笑う。
もう今はいない友人たち。あなたのようでいて、あなたではないあなた。
これから、壊れていく世界。
でも、あなたといると途端に欲が無くなるのはどうしてだろう?
今では思う。記憶だけがあればいいと。
あなたとこうして一つになれた記憶と、あなたと仲間たちと過ごした、人生で一番忙しかったあの一週間。それ以上は手ぶらでいこう。時間の先へ……先へ……。
スタンドに刻み込む、みんなの名前を、思い出を手に。
時は再び動き出す。父の目指した『天国』がもうじきやってくる。ぼくたちにはその『天国』の意味は分からない。だけどぼくはその先に、まだ『希望』を見る。
運命の矢はぼくの体の中。左肩に浮かぶ星形の痣を指し続ける。
隣に星を見る人さえいれば不安もない。
雨はやんで虹が出るだろう。
新しい世界が始まる。ぼくのそばには、笑うあの人がいて。
ぼくの中には、あの一週間と少しがくれた、みんなの意志がまだ残っていて……。
それは、『希望』を目指す原動力。
―― Fine